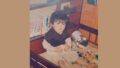私たちが日常で「ちょっと覚えておく」ことは、とても当たり前のようでいて、実は脳の中ではとても大切な役割を果たしています。
例えば、電話番号をメモする前に暗記する、買い物リストを頭の中で思い浮かべる――これらはすべて、短期記憶 の働きによるものです。
短期記憶は、必要な情報をほんの短い時間だけ保存し、すぐに取り出せるようにしてくれる、いわば「脳のメモ帳」のような存在です。
しかしその反面、時間が経つとすぐに消えてしまったり、新しい情報に邪魔されたりして忘れやすいという特徴もあります。
では、短期記憶はどのくらいの時間・どのくらいの量を覚えておけるのでしょうか?
そもそも私たちはなぜ忘れるのでしょうか?
そして、短期記憶を少しでも強化するにはどうすればいいのでしょうか?
今回は、短期記憶の基本的な仕組みと、覚えておくためのコツ、
さらに「作業記憶(ワーキングメモリ)」との違いや、最新の記憶モデルについても分かりやすく解説します。
そもそも短期記憶とは?
短期記憶(一次記憶、能動記憶とも呼ばれます)とは、必要な情報を一時的に保存し、すぐに取り出せる状態にしておく能力のことです。
例えば、電話番号をメモする前に暗記しておく、買い物リストを頭の中で確認する――これらはすべて短期記憶の働きです。
短期記憶ではどのくらい覚えていられるの?
短期記憶の特徴は、保持できる時間がとても短いことです。リハーサル(繰り返し思い出す作業)をしなければ、平均的には 数秒から20秒程度 と言われています。
また、容量にも限界があり、人が一度に覚えられる情報は有名な「7±2項目」説で知られていましたが、現在では「4±1項目」が妥当という研究もあります。
記憶のマジカルナンバー4±1とは?記憶が定着する具体的な方法を解説
短期記憶の忘却には大きく2つの説がある
① 自然消滅説(減衰説)
- 短期記憶に入った情報は、時間の経過とともに自然に弱まって消えていくという考え方。
- 代表例:数字を頭の中で繰り返さずにいると、数秒〜20秒ほどで思い出せなくなる。
仕組みのイメージ
脳内の神経ネットワークの活性状態が徐々に弱まり、記憶の痕跡(トレース)が消えてしまう。
② 干渉説(妨害説)
- 忘れるのは時間が経つからではなく、新しい情報が入ってきて古い情報が邪魔されるからという考え方。
- 代表例:電話番号を覚えようとしていたのに、話しかけられた途端に忘れる。
仕組みのイメージ
短期記憶の容量は限られているため、新しい情報が入ると、既にあった情報が上書きされる。
実際はどっちが正しいの?
結論としては、「自然消滅と干渉、どちらも影響している」と考えられています。
- 何もしなければ自然に記憶は弱まる(減衰説)。
- さらに新しい刺激や情報が入れば、干渉されて忘れやすくなる(干渉説)。
この両方のメカニズムで、短期記憶は忘却されると言われています。
短期記憶の強化する2つのコツ
①記憶時間を伸ばし、長期記憶へ「リハーサル」
そこで重要なのが リハーサル(rehearsal)、これは「繰り返し思い出すこと」です。
- 頭の中で繰り返す
- 声に出して確認する
- 何度も書いてみる
こうすることで、記憶は短期記憶内にとどまりやすくなり、さらに繰り返すことで長期記憶に移行する確率も高まります。
②記憶する量を増やす「チャンキング」
短期記憶には限界がありますが、「チャンキング」というテクニックを使えば、覚えられる量を効率的に増やせます。
チャンキングとは、たくさんの情報を「意味のあるかたまり(チャンク)」にまとめる ことで、短期記憶に入る情報の量を効率的に増やす方法です。
人の短期記憶には、一度に覚えられる情報の数に限界(約4±1チャンク) がありますが、1チャンクの中に含める情報量を増やすことで、実質的に覚えられる情報が増えます。
✔ ばらばらを「まとまり」にする
✔ 自分にとって意味のある形にする
✔ ストーリーやイメージで覚える
✔ 繰り返し練習する
記憶の仕組み
記憶の仕組みは大きく、
- 感覚記憶 →
- 短期記憶 →
- 長期記憶
の3段階で説明されます。
目や耳から入った情報は一瞬だけ感覚記憶に保存され、その後、必要なものだけが短期記憶に移ります。さらに繰り返し使われた情報だけが長期記憶へと転送され、長期間覚えていられるのです。
私たちの記憶は、昔から「感覚記憶 → 短期記憶 → 長期記憶」という 別々の箱(ストア)に分かれている というモデル(モーダルモデル)が主流でした。
しかし近年の研究では、「短期記憶と長期記憶を完全に別々のシステムとして考えるのは不自然では?」という考え方も出てきました。
これが ユニタリーモデル(統合モデル) と呼ばれる考え方です。
ユニタリーモデル(統合モデル)とは?
- 短期記憶は、長期記憶の一部が一時的に活性化した状態にすぎないと考える。
- 新しい記憶が一時的に活性化し、使われなくなると自然に減衰していく。
- 記憶は「短期か長期か」で線引きできるのではなく、連続したグラデーションのように繋がっている と捉える。
ユニタリーモデルを支持する現象の一つが、近時性効果 です。
単語リストなどの記憶テストで、最後の方に出てきた項目ほど覚えている確率が高くなるという現象です。たとえば10個の単語を順番に聞いて覚える場合、
- 最初の数個(プライマシー効果)も覚えやすい
- 最後の数個(近時性効果)は特に覚えやすい
- 真ん中あたりは忘れやすい
仕組みとしては、ピークエンド効果と似ていますね
| 項目 | 近時性効果(Recency Effect) | ピークエンド効果(Peak-End Rule) |
|---|---|---|
| 主な分野 | 認知心理学(記憶の順序効果) | 行動経済学・感情心理学(印象評価) |
| 起こる場面 | 単語リストの記憶などの順序付き情報 | 出来事の全体評価や思い出すとき |
| 関係する記憶段階 | 保存と想起 | 符号化・保存・想起まで幅広く |
| 仕組み | 直近の情報が活性状態で残りやすい | 強い感情(ピーク)と終了時の印象が深く符号化される |
| 何に影響する? | 項目の想起率 | 出来事全体の印象評価 |
| 例 | 買い物リストの最後の3つが覚えやすい | 旅行の一番楽しかった瞬間と帰り際の印象で「良い旅だった」と感じる |
| 実用例 | 記憶テスト、勉強の暗記法 | プレゼンの締め方、接客・体験設計 |
| 説明モデル | 順序位置効果(短期記憶の活性) | 感情強度と評価バイアス |
作業記憶(ワーキングメモリ) との違いは?
「短期記憶」と混同されやすいのが 作業記憶(ワーキングメモリ) です。
短期記憶は「一時的に保存するだけ」ですが、作業記憶は「保存しながら頭の中で情報を操作する」役割も含まれます。
例えば、電話番号を覚えるだけなら短期記憶ですが、複数の数字を足したり順序を入れ替えたりするときは作業記憶が活躍しています。
| 項目 | 短期記憶 | ワーキングメモリ(作業記憶) |
|---|---|---|
| 定義 | 情報を一時的に保持する機能 | 情報を一時的に保持しながら操作・処理する機能 |
| 主な役割 | 覚えておくだけ | 覚えつつ思考や計算などを行う |
| 例 | 電話番号を暗記する | 電話番号を逆順に言う、計算しながら覚える |
| 保存時間 | 数秒〜20秒程度 | 数秒〜数十秒(作業に応じて延長) |
| 容量 | 限定的(4±1チャンク程度) | 同じく限定的だが、操作の複雑さで負荷が変わる |
| 脳内の主な部位 | 側頭葉や頭頂葉 | 前頭前野(特に前頭連合野) |
| 関連するモデル | モーダルモデル | バデリーのワーキングメモリモデルなど |
| 使用場面 | 一時的な記憶保持のみ | 言語理解・問題解決・推論などの思考活動 |