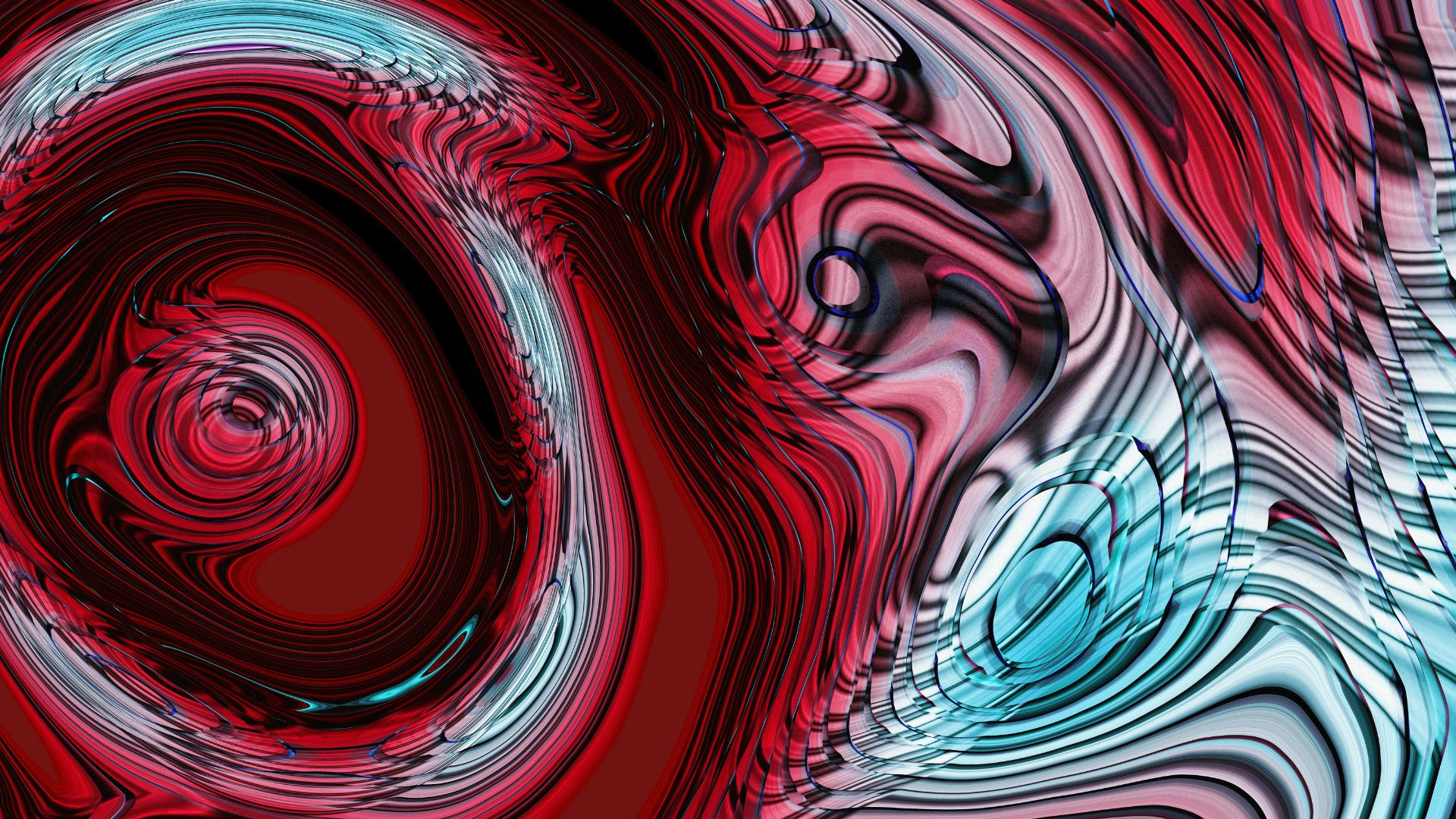「白黒思考やマイナス思考を治したい。でも、思考を治すのが怖い。改善したのに、どうして怖いんだろう」
認知の歪みは治したほういいと思っていても、なかなか踏み切れないことがあります。
認知行動療法で考え方を変えようと言われると、自分を見失うようで怖さを感じていました。
だけど、「自己否定を治したい」と思ったときは怖さはありませんでした。
こちらも思考なのになぜだったのか?
当時の僕は認知の歪みによって少し気持ちが楽になっていたからです。
自己否定は「苦しさしか感じない」という感覚があり、心から治したい想いがあったので治すことに抵抗がなかったんだと思います。
実際には、自己否定も自分の気持ちを少し楽にする効果はありますが、やめたい想いのほうが強かった。
認知の歪みを治すのに大事なこと
認知の歪みを治すのに大事なことがあります。
それは「認知の歪みを治していく」と、きちんと意思を持つことです。
何を当たり前のことを、と思うかもしれません。
でも、重要なことです。
なぜなら、認知の歪みは必要があって生まれた歪みだからです。
けっして、あなたを苦しめるために生まれているのではなく、あなたを楽にするために生まれているものなんです。
ただ、無意識で生まれる「楽」とは、「目先のこと」「できるだけ考えなくする」を重視します。
そのため、長い目で見ると苦しくなったり、トラブルが起きたりします。
ダイエットをしているのに、目先のお菓子の誘惑に負けるのと同じ理屈です。
脳はあなたをダイエットの我慢から自由にするため、お菓子の喜びを届けるためにしています。
ただ、長期的に考えてはくれません。
ただ誘惑を乗り越えた先に、「望んだ楽しい日々」があります。
今回、お伝えする「認知の歪みを治すための科学的な10の方法」は手軽にできる認知行動療法です。
でも、「認知の歪みを治していこう」という気持ちがブレてしまうと、治すのは難しくなります。
認知の歪みを整えるとは、現実的に自分や環境を見ていくことなので、ストレスがかかることでもあるからです。
なので、認知の歪みは少しずつ整えていくことが大事です。
少しずつ整えていくと、途中で「あ!」というひらめきのような感覚で、認知の歪みが解消されていきます。
ただ、必要があって生まれた歪みなので少しは残るかもしれません。
でも、それでOKです。
猫背の人が背筋をまっすぐする、といっても。
背筋は本当にまっすぐなのではなく、自然なレベルでゆるやかに曲がっているものです。
認知の歪みが完全になくなるのは不自然なことで、やや認知の歪みが残るぐらいが自然で現実的な見え方なんです。
認知行動療法で、認知の歪みを治すには、「認知の歪みを否定しないこと」が大切です。
その認知の歪みから生まれる考え方が、自分にとってどういう存在かを知り、そこから自分はどのように考えて行動したほうがいいか?と考えを見直していくことが認知行動療法の考え方です。
認知行動療法は思考を変えるといいますが、個人的には思考をクリアにして、感情や行動のバランスを整えていく方法です。
認知の歪みを治すための科学的な10の方法
今回はワシントン州立大学の「認知の歪みを治すための科学的な10の方法」を参考にお伝えします。
執筆者はジョン・M・グロホル博士です。
臨床心理学者であり、オンラインメンタルサポートの第一人者です。
信頼性があり、とても分かりやすて使いやすく、実際に僕がメンタルを整える上で行ってきた知識です。
認知の歪みは、個人が現実を誤って解釈し、否定的な感情や行動を引き起こす思考の偏りです。
そのため、否定的な感情や行動につながっている場合、ポジティブな面も見ていくのが大切になっています。
1.コスト・ベネフィット分析
コスト・ベネフィット分析は、認知の歪みのメリットとデメリットを評価して、より良い考え方をする方法です。
メリットを考えるときは、短期的なメリットではなく、長期的なメリットにつながるかを意識することが大事です。
コストベネフィット分析の方法
①認知の歪みを特定する
②特定した認知の歪みのメリットとデメリットをリスト化
その思考を持つことで得られるメリットとデメリットを書き出す
③メリットとデメリットを見て評価する
デメリットがメリットを上回る場合、その思考を変える動機付けになる。
メリットをデメリットを考えたと、バランスの良い思考に変わっていく。
※思考だけではなく、行動なども同じ方法をとるのがおすすめです。
2.証拠の検討
証拠の検討とは、自分の思考や感情から一歩引いて、それが事実に基づいているかどうかを客観的に評価することです。
例えば、自分に対して「私は無能だ」と思う場合、その思考が事実に基づいているかどうかを検証します。以下のステップで行います。
証拠の検討の方法
①感情と事実を分ける
自分が感じていることと実際に起こったことを分ける。
頭で考えるより、紙に書き出した方が分かりやすいです。
②意見と事実を区別する
例えば、「仕事の接客でミスした私は無能だ」の場合。
「私は無能だ」というのは意見です。事実は「今日、接客でミスをした」です。
こちらも紙に書き出した方が分かりやすいです。
③具体的な証拠を探す
自分が成功した経験や他人からのポジティブな感想など、肯定的な事実や情報を見つける。
認知の歪みは非現実であることが多いため、事実と反している場合があります。
その場合は、「事実はこうだよ」と自分に教えてあげるだけでも認知の歪みは解消されていきます。
3.グラデーション思考
グラデーション思考とは、白黒思考のように極端に考えるのではなく、白黒の間のグラデーションで考えていく方法です。
白黒思考は0か1か思考、0か100か思考とも呼ばれます。
グラデーション思考は0~1の0.1,0.2、0.3…や0~100の1,2,3….33,34,35…85,86…などの間を見る方法です。
グラデーション思考の方法
①部分的な成功を認める
完全な失敗と考える代わりに、部分的な成功として評価します。
「〇%」「10点満点だと〇点」「5段階評価だと〇点」などと考える
例えば、成功と失敗ではなく、「〇%の成功」と考えると白黒思考から抜け出せます。
②現実的に評価する
例えば、「ダイエット中にアイスを一口食べたから全部台無しだ」と考えるのではなく、「一口くらいなら全体の成功にはほとんど影響しない」と考える。
こちらも「〇%」「10点満点だと〇点」「5段階評価だと〇点」などと考てもOKです。
おちいりやすい罠としては、「白黒思考をグラデーション思考にしなくちゃいけない」と考えることです。でもはこれは「白黒思考は悪い」という白黒思考での判断です。
「人間なんだから、たまには白黒思考ぐらいにはなるよね」とやわらかく捉えていきましょう。
否定的な感情や行動につながらなくするだけではなく、現実的であることも大事なことです。
4.特定と評価:認知の歪みを特定する
認知の歪みが自分に当てはまっているか特定して、気づくだけでも、一歩前進になります。
気づくことで整える意識が、自然と働くようになるからです。
姿勢でも同じですよね。猫背と気づかないとそのままですが、猫背と気づくと「背筋を伸ばそう」って思えるようになります。
ただ特定するだけだと、どの認知の歪みから改善すればいいかが分かりません。
そのため、特定だけではなく、評価も同時に行うのがおすすめです。
10個の認知の歪みの中でどれが強くいか弱いかを知ることで、どの認知の歪みから取り掛かればいいかが分かるようになります。
総当たりするよりは、10倍速いです。
しかも、認知の歪みは影響しあっているので、強い認知の歪みを整えると、自然と他の認知の歪みも整ってきます。
特定と評価は、後述する「12の認知の歪みの特徴とそれぞれの解決法」を読みながら、行うことがおすすめです。
もちろん、YouTubeメンバーシップ動画で見ながら行っていただいてもOKです。
特定×評価の方法
①メモの用意
②文章を読みながら、または動画を見ながら5点満点で採点する。
③上位1~3つの認知の歪みを整えていく
※採点(厳密に考えずに、ある程度感覚でOKです)
5点:とても当てはまる
4点:かなり当てはまる
3点:当てはまる
2点:やや当てはまる
1点:あまり当てはまらない
日常生活で意識するだけでも、自然と整ってきます。
認知の歪みは「気づくだけ」でも効果があるからです。
この「特定×評価」を定期的に行うことで、「どの認知が歪みやすいか?」も分かってきます。
はじめのうちは慣れないので、3日ほどは続けて行うことをおすすめします。
認知の歪みの理解が進み、少しずつ「評価の点数付け」の精度が高まってきます。
日記を書いて行うと、より効果的です。ただ、認知の再構成は継続が大切なので、まず継続できる方法で行っていきましょう。
5.セマンティック法
セマンティック法は、認知の歪みの思考を別の表現に置き換える方法です。
言葉の意味をやわからくすると、捉えていただければOKです。
セマンティック法の具体例
「〇〇すべきだ」→「〇〇できるといいな」
「いつも失敗する」→「失敗することもあるけど、成功することもある」
「完璧にする」→「より良くする」
「いつも悲しい」→「悲しいこともあるけど、笑うこともある」
「毎日しなきゃいけない」→「3日1回できればOK」
セマンティック法は、言葉のストレッチ。やわらかくしていきましょう。
6.ダブルスタンダード法
ダブルスタンダード法は、2つ以上の意見を持つことです。
自分自身に対して厳しいルールや評価をする場合に使えます。
例えば、自分へのアドバイスではなく、他人へのアドバイスと考えると、2つの意見が持てます。
2つの意見を持つことで、視野が広がり、認知の歪みが解消されていきます。
重要なのは、他人に対するように自分に思いやりを持って理解していくことです。
ダブルスタンダード法の方法
①認知の歪みに気づく
特定×評価を使ってください。
②気づいた認知の歪みに対して、自分にアドバイスする
③気づいた認知の歪みに対して、友人に対するようにアドバイスする
友人でなくてもいいです。架空のキャラでもOKです。
自分が思いやりを持ってコミュケーションができる相手であればOKです。
慣れてくれば1人だけではなく、「別の人の場合はどうアドバイスするかな?」と考えるとさらに視野が広がります
④②③の違いを見て、認知をやわらげる
難しい場合は、紙に書き出して行うのがおすすめです。
紙に書き出したほうがより客観的になれるので、効果が高まります。
慣れてくると頭だけでできるようになります。でも、たまに紙に書き出すことをおすすめします。
頭だけでできているか確認するためです。
似た方法として「セルフコンパッション日記」があります。
こちらは「自己否定をなくし自分に思いやりを持つ」を強めに意識したものです。
ちなみに僕はセルフコンパッション日記から、このダブルスタンダード法を使い始めました。
7.調査法
調査法は、自分の考えが現実的かどうかを他人に尋ねる方法です。
シンプルで効果的な方法です。
調査法の方法
①認知の歪みに気づく
②気づいた認知の歪みについて、誰かに質問する
③複数人に質問する
※できればグループが違う人たちに聞くのがいいです。同じグループだとグループでの価値観が反映されるからです。
他の認知の歪み解決法を行ったあとで、さらに調査法を行うと、効果が高まります。
多くの人の声を聞くと、孤独感が薄まる効果もあります。
いろいろな考えを知ることができるからです。
8.定義の再考
定義の再考は、自分が使っているラベルや定義を見直す方法です。
ここでは3つのRを使います。
例えば、まったく掃除ができない。を振り返る。
本当に「まったく掃除ができていなかったか?」→全部はできなかったけど、床に置いてある本やクッションは片付けることはできている。
リフレーミング。掃除はできなかったけど、その分、休むことができた。見たかったドラマを見ることができて、ストレス解消できた。
リアプレイザル(内面を捉えなおす)。掃除をできずに自己否定している。掃除のハードルが高すぎるサインかもしれない。まずは、5分だけ掃除するから始めてみよう。
定義の再考の方法
①認知の歪みで使っている言葉を書き出す(考える)
例:まったく掃除ができない。
②それぞれ単語の定義する
例:まったく~できない→なにもできない
掃除→部屋や場所を綺麗にする活動
③はじめの認知の歪みの言葉は正しかったか考える
例:思った通りに掃除はできなかったけど、ゴミ出しや机の上の片づけはしている。
だから、まったくできていない訳ではない。
できていなかったのは、本棚の片づけだけだった。
定義の再考と聞くと難しく聞こえますが、「なぜそう思うのか?」と自分に問うだけでも、認知の歪みをとらえなおすことができます。
9.再帰属法
再帰属法とは、問題の原因を自分以外に移す方法です。
自責が強い方が、問題の原因を他に移すことで、否定的な感情をやわらげることができます。
具体的には次のように行います。
再帰属法のやり方
①自責が強い考えを特定する
②自分以外に責任が移せるものを探す
③責任を分散する
具体例
①自責が強い考えを特定する
例「友だちが最近冷たい。きっと私のことを嫌いになったんだ」
②自分以外に責任が移せるものを探す
例「友だちが最近冷たいのは、仕事やプライベートで他に嫌なことがあったからかも」
体調(疲れ、睡眠不足など)、他の人間関係、悩み、
③責任を分散する
例「自分に何か悪いことがあったかもしれないけど、仕事やプライベートが原因かもしれない」
再帰属法によって自己否定癖がやわらいで、気持ちが楽になる。
自分だけが悪いのような非現実的な思考がなくなる。
「自責がいい?」と「他責がいい?」とよく言われますが、ポイントが3つあります。
自己責任の割合は大きければ大きいほどいい→コントロールできるものが多い。自分軸で生きやすい
自分にはどうしようもない→なんとかすることができる
①自分がコントロールできることと、コントロールできないことを分ける。
コントロールできることを増やしていく。
コントロールできないことまで責任を感じるのは、非現実的で苦しみを生みます。
②「責」とは原因があるだけで、罰を与えることでありません。
自責だと自分を否定する、他責だと相手を否定するのではなく、自責がある場合は「改善・対処していく」。他責がある場合は「手放していく」。
責任→罰や否定(攻撃)にとらわれると、自責・他責はバランス以前の話になるのでご注意ください。
③自分がコントロールできることを増やすのが大切。
自責が良いと言われることがあるのは、「自分でコントロールできることを増やす」のが良いからです。
例えば、「運動ができないのは時間がないせいだ」ではなく、「どうすれば運動ができるようになるのかな?」とまず自分のコントロール内にもっていくことが大事です。
自分のコントロール内にもっていく中で、どうしてもコントロールできないものは手放していくのが大事です。
10.実験法
実験法は、自分の否定的な思考が現実的な考えかどうかをテストする方法です。
テストを繰り返すことで、認知の歪みが現実的な考えかどうかを判断していきます。
実験法の方法
①認知の歪みに気づく
例:仕事を完璧にしなくちゃいけない。でないと失敗だ
②実験の計画を立てる
「認知の歪み」が現実的な考え方かを試す。
例:仕事を完璧ではなく、時間内で、苦しくない範囲で行ってみる
③実験の予想をする
例:完璧にしないと、上司に叱られる。仕事も進まない。
④計画を実行する
⑤実行した結果を評価する
予想と違うかどうかがポイント。
例①「上司から注意はあったが、怒って叱るというものではなかった」
例②「まわりの人が思ったよりもサポートしてくれて、むしろよりうまくいった」
例③「力が抜けたことで、いつもよりもうまくできた」
例④「上司に叱られたが、完璧ではなく、一部分だけの注意だった」
⑥認知の修正
⑤の結果をもとに認知を修正する。
例①「完璧ではなくてもある程度評価される。注意ポイントを改善していけばいい」
例②「完璧にしようとしなくても助けてくれる人がいる」
例③「完璧と考えない方がうまくいくことがある」
例④「仕事は完璧ではなく、要点をおさえておく」
認知の歪みを整える実践ワーク4ステップ
1.特定×評価をまず行う
【特定×評価】を行って、まず自分の認知の歪みを知りましょう。
文章を読みながらでもいいですし、動画を見ながらでも良いです。
だいたい問題は、「現状を知る」から始まります。
2.点数が高いものから認知の歪みを整えていく
【特定×評価】の結果、点数が高いものから認知の歪みを整えていってください。
はじめは1つだけでもいいです。しっかり行いたい場合でも3つまでにしてください。
認知の歪みはお互いに影響しあうので、点数が高い認知の歪みを整えるだけで他の認知の歪みも整ってくるからです。
整える認知の歪みの数が増やすと「面倒だな…」と思ったり「何から手を付ければいいのか分からない」と行動しにくくなったりします。
もしも、点数が似ていて、どれから手をつけて良いか分からない場合は、次の認知の歪みからでもOKです。
【特定×評価】ですべての点数が高い場合、5段階の評価が白黒思考によってうまくできていない可能性があります。
白黒思考:極端さが現実とのズレを大きくするので、点数が高いなら優先度が高い
マイナス思考:ポジティブなことをマイナスで考え、幸福度がさがりやすい
※認知の歪みは「極端」と「マイナス」が中心なので、この2つを対策すれば自然とほかのもの整ってくる。
3.紹介した解決法を一通り行う。相性のいいものを見つける
紹介した解決法は、軽くでも良いので一通りやることをおすすめします。
「自分にとってやりやすいか?」
「効果があるか?」をチェックしましょう。
自分にとってやりやすく効果がある解決法を続けていくのが大切です。
認知の歪みだけではなく、他のトラブルにおいても、その解決法は役立つものになるからです。
解決法も独立しているものではなく、1つができるようになってくると、他のものもできるようになってきます。
例えば、ダブルスタンダード法ができるようになると、人の話を聞きやすくなり調査法がしやすくなります。
グラデーション思考ができるようになると、メリットとデメリットのバランスをとりやすくなりコストベネフィット分析がしやすくなります。
4.どれが良い方法か分からない場合、認知の歪み別おすすめ解決法を行う
12の認知の歪みパターン別におすすめの解決法を3つ載せています。
どの解決法から試せばいいか悩んだときは、参考にしてください。
ただし、どの認知の歪みでも【特定×評価】は必ず行ってください。まず知ることは大事です。
12の認知の歪みの特徴とそれぞれの解決法
ベックマンの認知の歪みは10個ですが、「結論の飛躍の読心術と未来予測」と「拡大解釈と過小評価」を別々に分けているので12個になっています。
1.白黒思考(全か無かの思考)
物事を極端に捉えて、白か黒か、0か1かで考えます。0~1の間の考え方をしません。
認知の歪みを整えて再発しやすい思考です。
「絶対に」「まったく」「完璧」などの言葉を使いやすいです。
具体例
「一度の失敗で、自分には価値がないと感じる。」
「一つの部屋が散らかっていると、家全体が汚いと感じる。」
「一日運動をサボった。だから、もう運動する意味はない。」
「一度のミスで全てが台無しだ。」
「成功しなければ、完全な失敗だ。」
メリット
・決断が早くなる
・行動が早くなる
・ストレスが減る
・目標達成をしやすい
デメリット
・現実とズレが出てくる
・柔軟性がなくなる
・対人関係の問題が出る
・ストレスが増える
・自己肯定感が下がる:失敗
・誤解や偏見が増える
白黒思考(全か無かの思考)のおすすめ解決法
・グラデーション思考:白と黒の間を考える
・証拠を検討する:その白黒思考と事実のズレを見る
・ダブルスタンダード法:視点を増やすことで思考が柔軟になる
2.過度な一般化
1つの出来事や経験をもとに、すべてが同じように悪い結果になると考えることです。
「すべて」「みんな」「毎回」などの言葉を使いやすいです。
具体例
「一度失敗したから、私は他のことをやっても失敗する。」
「家が散らかっているから、私は整理整頓が苦手だ。」
「友だちが怒った。自分は何をしても怒られる」
「いつも失敗ばかりする。」
「誰も私のことを理解してくれない。」
メリット
・決断が早くなる
・行動が早くなる
・学習が効率的
・未来予測がしやすい
デメリット
・現実とズレが出てくる
・柔軟性がなくなる
・対人関係の問題が出る
・ストレスが増える
・自己肯定感が下がる:失敗
・誤解や偏見が増える
・成長がとまる
・問題解決ができない
過度な一般化のおすすめ解決法
・証拠を検討する:一般化せずに事実を見る
・実験法:一般化してよかったかテストして確かめる
・調査法:他の人の話を聞く(それぞれの意見が聞ける)
3.心のフィルター
一部の情報(特にネガティブな情報)にのみ集中し、他の情報を無視することです。
「やっぱり」「まったく」「毎回」などの言葉を使いやすいです。
具体例
「小さなミスにこだわって全体を見失う。」
「一つの批判だけに注目する。」
「全体の成功を無視して小さな失敗にこだわる。」
「一つの悪い出来事が全てを台無しにする。」
「肯定的な意見を無視して否定的な意見だけに注目する。」
メリット
集中力の向上:重要な情報に集中しやすくなるため、効率的に問題解決ができることがあります。余分な情報に惑わされず、必要なデータだけをピックアップできます。
リスク管理:危険や問題点に特化して注意を払うことで、潜在的なリスクを見逃さずに済みます。
デメリット
偏った見方:ポジティブな情報を無視し、ネガティブな側面にばかり注目するため、全体像を正確に把握しにくくなります。バランスの取れた判断が難しくなります。
精神的ストレス:ネガティブな情報にばかり焦点を当てることで、ストレスや不安が増加します。
心のフィルターのおすすめ解決法
・証拠を検討する:プラスの証拠を見つける
・グラデーション思考:マイナスを白黒にせず、間を見る
・ダブルスタンダード法:視点が増えることで視野が広がる
4.マイナス思考
ポジティブな出来事や成果を無視したり、価値を低く見積もることです。
「どうせ」「できてない」「最悪」などの言葉を使いやすいです。
具体例
「テストで90点を取ったけど、100点じゃないから意味がない。」
「上司に褒められたけど、それは単なる励ましに過ぎない。」
「体重が減ったけど、まだ理想体重にはほど遠い。」
「友だちが褒めてくれたけど、気を使っているだけだ。」
「絵を描いたけど、プロには遠く及ばないから意味がない。」
メリット
リスク認識:物事のネガティブな面を重視することで、潜在的なリスクや問題を事前に認識し、対応策を考えることができます。
準備の向上:ネガティブな結果を予測することで、予防策を講じるなどの準備がしやすくなります。
デメリット
自己評価の低下:自分の成功やポジティブな出来事を過小評価するため、自信を喪失しやすくなります。
精神的負担:常にネガティブな結果を考えることで、ストレスや不安が増加します。
マイナス思考のおすすめ解決法
・コストベネフィット分析:デメリットだけでなくメリットも見る
・証拠を検討する:マイナス思考が事実か確認する。
・ダブルスタンダード法:複数視点で、柔軟な思考を持つ
5.結論の飛躍:読心術
十分な証拠もないのに、ネガティブな結論に飛びつくことです。
読心術の場合、誰かが実際には考えていないことを考えていると信じたりすること。
具体例
「彼は本当は私のことが好きではない。」
「彼は私を軽蔑している。」
「友達は私を本当の友達と思っていない。」
「彼女は私がいない方がいいと思っている。」
「彼は私の話を聞きたくないと思っている。」
メリット
対人関係の調整:他人の意図や感情を推測することで、適切な対応やコミュニケーションが取れる場合があります。特に人間関係が重要な状況では有利です。
迅速な反応:直感的な判断が必要な状況では、他人の意図を即座に理解することで迅速な対応が可能です。
デメリット
誤解のリスク:他人の考えや意図を誤解することが多く、人間関係に摩擦を生じやすくなります。
ストレスの増加:ネガティブな推測が多い場合、不必要な不安やストレスを引き起こします。
結論の飛躍:読心術のおすすめ解決法
・調査法:他人の考えを推測で終わらせずに、聞く
・実験法:自分の推測が当たっているかテストする
・証拠を検討する:自分の推測が事実か確認する
6.結論の飛躍:未来予測
「未来が〇〇になるだろう」と未来を予測すること。基本的にネガティブな未来予測です。
具体的
「友達は私を裏切るに違いない。」
「彼は私を見捨てるだろう。」
「私は孤独なままだ。」
「この病気は治らない。」
「この試験に落ちるに決まっている。」
メリット
リスク予防:未来のネガティブな結果を予測することで、事前に予防策を講じることができます。
計画性の向上:予測に基づいて計画を立てることで、準備が整いやすくなります。
デメリット
過度な不安:未来のネガティブな予測に基づく過度な不安や心配が、現在の行動や決定に悪影響を及ぼします。
挑戦の回避:失敗を恐れて、新しい挑戦や機会を避ける傾向が強まります。
結論の飛躍:未来予測のおすすめ解決法
・実験法:未来予測が正しかったかどうかをテストする。
・証拠を検討する:未来予測が正しかったか事実を確認する
・コストベネフィット分析:ネガティブな未来予測の結果のメリット・デメリットを見る
7.拡大解釈
小さな問題を大げさに考えること。
「絶望的だ」「どうしようもない」「取り返しがつかない」などの言葉を使いやすいです。
具体例
「小さなミスで全てが台無しだ。」
「失敗は取り返しがつかない。」
「失敗はいつも私のせいだ。」
「他の人はもっと努力している。」
「他の人はもっと大変だ。」
メリット
問題意識の向上:小さな問題を重要視することで、早期に対処する動機づけになります。
自己改善の機会:問題を大きく捉えることで、自己反省や改善点を見つけやすくなります。
デメリット
過剰なストレス:小さな問題を大きく捉えすぎるため、過度なストレスを感じることがあります。
自己否定の強化:自己評価が低下し、自己否定的な思考が強まることがあります
拡大解釈のおすすめ解決法
・証拠を検討する:大きくとらえず、事実を確認する
・グラデーション思考:白黒的な拡大解釈を防ぐ
・ダブルスタンダード法:複数視点で視野が広がる
8.過小評価
重要なことを過小評価することです。
「大したことない」「運が良かっただけ」「誰でできる」などの言葉を使いやすいです。
具体例
「他の人はもっと優れている。」
「成功しても、それは大したことない。」
「私の努力は無意味だ。」
「誰でもできることしかできない。」
「私の役割なんて大したことない。」
メリット
現実的な目標設定:自分の能力を過小評価することで、無理のない現実的な目標を設定しやすくなります。
他者への過度な期待回避:他人の能力や成果を過小評価することで、過度な期待を避け、失望を減らすことができます。
デメリット
自信の喪失:自分の能力や成果を過小評価するため、自信を失いやすくなります。
挑戦の回避:成長や挑戦の機会を見逃し、自己成長の機会を失うことがあります。
過小評価のおすすめ解決法
・証拠を検討する:自分の成功やポジティブな事実をか確認する。
・ダブルスタンダード法:複数視点で、評価を公平にする
・実験法:自分の能力をテストしていく
9.感情的理由付け
感情がそのまま現実を反映していると信じることです。
「感じるから」「思うから」「どうせ〇〇だから」などの言葉を使いやすいです。
具体例
「私は無価値だと感じるから、本当に無価値なんだ。」
「私は嫌われていると感じるから、みんな私を嫌っているんだ。」
「私は孤独だと感じるから、本当に孤独なんだ。」
「私は不安を感じるから、何か悪いことが起こるに違いない。」
「私は疲れているから、何もできない。」
メリット
迅速な意思決定:感情に基づいて迅速な意思決定ができるため、緊急時に役立ちます。
感情認識の向上:自分の感情に基づいて行動することで、感情の認識と対処がしやすくなります。
デメリット
非合理的な判断:感情に左右されるため、論理的で合理的な判断が難しくなります。
一時的な感情の影響:一時的な感情に基づく決定が、長期的に不利な結果をもたらすことがあります。
感情的理由付けのおすすめ解決法
・証拠を検討する:感情ではなく事実で判断していく
・グラデーション思考:感情的な決めつけをやわらげる
・コストベネフィット分析:感情的理由付けのメリット・デメリットを評価する
10.べき思考
自分や他人に対して厳しいルールや評価を押し付けることです。
「~すべきだ」「~しなければならない」「~するのが普通だ」などの言葉を使いやすいです。
具体例
「もっと努力すべきだった。」
「失敗してはいけなかった。」
「常に完璧でなければならない。」
「いつもポジティブでいなければならない。」
「他人に迷惑をかけてはいけない。」
メリット
高い基準設定:自分や他人に対して高い基準を設定することで、自己成長や目標達成を促進します。
倫理的行動:道徳的・倫理的な行動を維持しやすくなります。
デメリット
過度なプレッシャー:自分や他人に対して厳格すぎる期待を抱くため、ストレスやプレッシャーが増加します。
柔軟性の欠如:べき思考に固執することで、柔軟な対応や適応が難しくなります。
べき思考のおすすめ解決法
・セマンティック法:「~すべき」を「~した方が良い」に変えていく
・コストベネフィット分析:べき思考のメリット・デメリットを評価する
・証拠を検討する:べき思考と考える理由を事実をもって評価する
11.ラベリング
自分や他人に対して極端でネガティブなレッテルを貼ることです。
例えば、「無能だ」「怠け者だ」「失敗者だ」「ケチだ」などの言葉を使いやすいです。
具体例
「私は失敗者だ。」
「私は無価値だ。」
「私は無能だ。」
「私は役立たずだ。」
「私はダメな親だ。」
メリット
迅速な認識:特定の行動や特徴を迅速に認識でき、情報の整理がしやすくなります。
予測と準備:ラベルを用いることで、予測や準備が容易になります。
デメリット
偏見と誤解:ステレオタイプに基づく偏見や誤解を招くことがあります。
固定観念:一度貼られたラベルが固定され、成長や変化を見逃しやすくなります。
ラベリングのおすすめ解決法
・定義の再考:自分や他人につけたラベルを見直す
・証拠を検討する:自分や他人につけたラベルの事実を評価する
・ダブルスタンダード法:複数視点でラベルをはがす
12.否定的な個人化
自分のせいで悪いことが起きたと過剰に責任を感じることです。
例えば、「私が悪い」「もっと〇〇していれば」「私が原因だ」などの言葉を使いやすいです。
具体例
「チームの失敗は全て私のせいだ。」
「家族の不和は私が原因だ。」
「友達がうまくいっていないのは私のせいだ。」
「子供の成績が悪いのは私が悪い親だからだ。」
「職場の雰囲気が悪いのは私がいるからだ。」
メリット
責任感の強化:自分の行動に責任を感じることで、問題解決に積極的に取り組む動機づけになります。
自己反省:自己反省のきっかけとなり、自己改善を図ることができます。
デメリット
過度な罪悪感:自分に関係のない問題まで責任を感じることで、過度な罪悪感を抱くことがあります。
精神的負担:過度に自己責任を感じるため、精神的なストレスが増加します。
否定的な個人化のおすすめ解決法
再帰属法:問題の原因を他の要因に置き換える
証拠を検討する:自分を責任を事実で評価する
コストベネフィット分析:自分を責めることの利点と欠点を評価する
まとめ
認知の歪みは「自分を守るため」に無意識に生まれた思考パターンですが、長期的には心や行動に負担を与えることがあります。
そのため、「認知の歪みを治していこう」と自分で意思を持ち、少しずつ整えていくことが大切です。
今回紹介した10の科学的な方法は、どれも手軽に実践できる認知行動療法に基づいており、自分に合った方法を見つけて継続することが、思考の柔軟性や現実的な視点を取り戻す鍵となります。
大事なのは、「認知の歪みを完全になくすこと」ではなく、「現実と調和した、より生きやすい思考スタイルに近づくこと」です。
認知の歪みは決して悪者ではなく、自分を支えてくれた一面もある存在。
だからこそ否定せずに、感謝を持って手放し、より良い考え方を育てていきましょう。