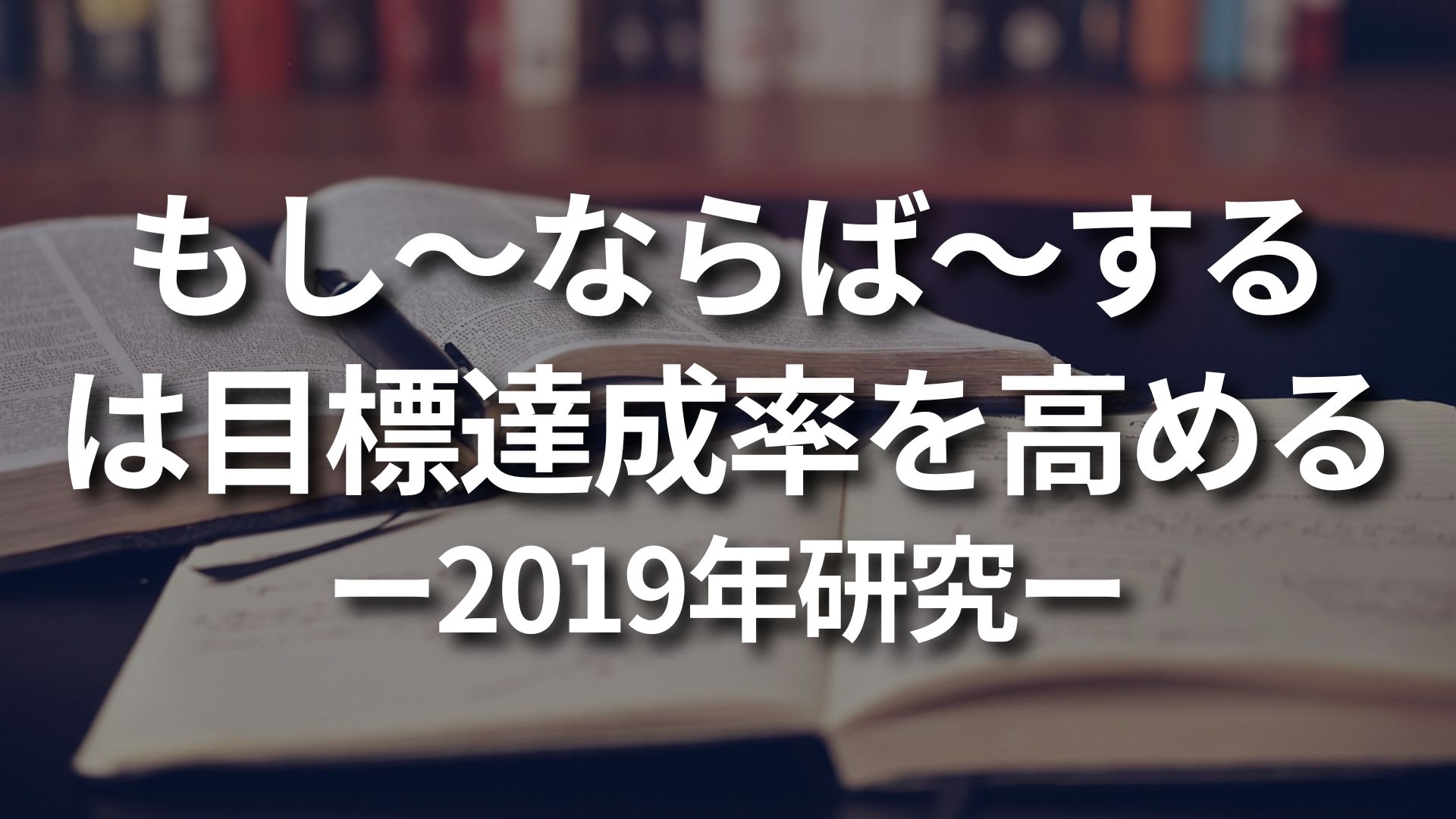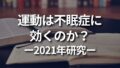行動科学や心理学の分野では、目標達成を促すための方法論が数多く研究されています。
その中でも「実行意図(implementation intentions)」は、目標を達成するための具体的な計画を立て、その計画を実際の行動に結びつける効果的な手法として注目されています。
本記事では、実行意図に関する最新研究をわかりやすく解説し、その効果や課題について紹介します。
【研究や論文は、chatGPTに著作権に配慮して、要点をまとめてもらっています。[ ]のメモは僕の意見・感想です】
▼結論
実行意図は「もし~ならば~する」という形式で行動計画を立てることで、目標達成率を高める戦略です。最新研究によれば、特に行動の自動化や柔軟な目標達成に効果がある一方で、状況が変わった場合や異なる場面では逆効果になるリスクも指摘されています。
▼内容の信頼性:8点/10点
本研究は、30年以上にわたって検証され続けた実行意図の有効性を複数の実験とメタ分析に基づいて解説しており、信頼性は高いと言えます。ただし、研究方法が学生や特定集団に偏っているため、一般化には限界があると評価されます。
▼何の研究か?
本研究は、「実行意図」が目標達成に及ぼす影響を検証したものです。実行意図とは「もし~ならば~する」という形式で、特定の状況でどのような行動を取るかをあらかじめ計画しておく戦略を指します。
▼研究した理由は?
多くの人が「目標を立てても実際には行動できない」という課題に直面しているため、効果的に目標を達成する方法を明らかにする必要がありました。その中で、実行意図が「行動を自動化する」効果を持つ可能性に着目し、研究が進められました。
▼結果はどうだったか?
研究結果では、実行意図を設定することで行動の自動化が促進され、目標達成率が向上することが確認されました。一方で、計画した状況と異なる場面では、その自動化が裏目に出て誤った行動を引き起こすリスクも示唆されています。また、身体的負荷を減少させる効果が確認されている一方で、逆に負荷を強調する結果となったケースもあり、使い方に工夫が必要であると結論付けられました。