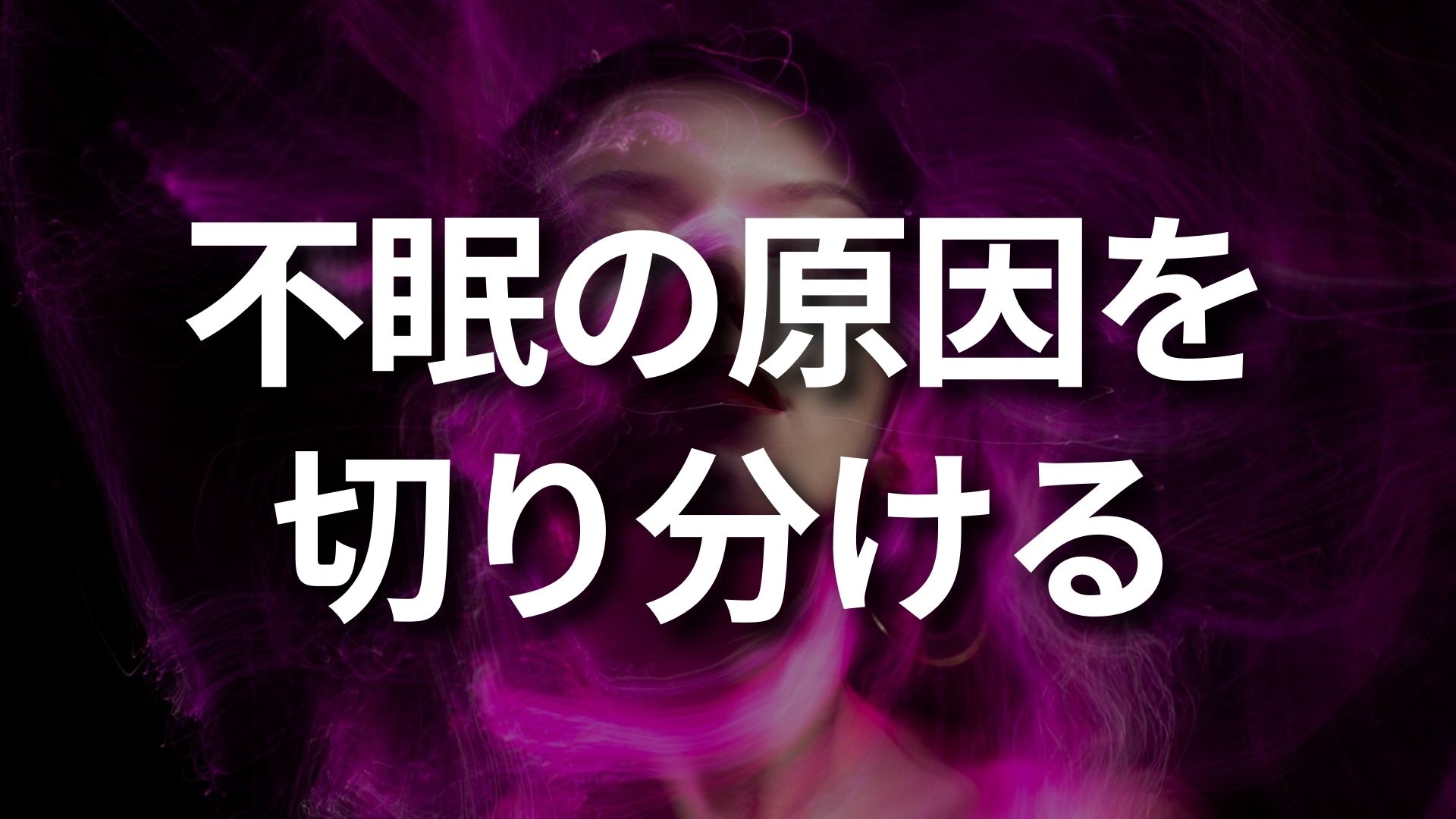「今日も4時間しか眠れていない。そんな毎日が、もう3か月以上も続いている…」
「眠れるときもあるけど、睡眠がなかなか改善しないのは何でだろう?」
「結局どうすれば、眠れるのかが分からない」
そんな悩みを抱えていませんか?
僕も以前は不眠症で悩んでいました。「どうすれば眠れるだろうか?」とリラックス法を試したり、朝に光を浴びたりしても、なかなか改善しませんでした。
結果、「何しても意味ないのでは?どうすればいいんだ?」と混乱し、リラックス法や朝に光を浴びることをやめてしまったこともあります。
その後、不眠症が改善したのは、「自分の眠れない原因」に気づいたからです。
不眠症が改善し、睡眠薬をやめたあとも安定して眠れているのは「眠れない原因をつぶしていっている」からです。
今回は、僕が不眠症のときだけではなく、現在も使っている「眠れない原因を見極める薬の使い方」をお伝えします。
眠れない原因を見極めるには「頭痛薬を使う」
眠れない原因を見極めるには「頭痛薬を飲んで眠りやすくなるかどうかを見る」方法があります。
頭痛薬は痛みや高ぶった気持ちを鎮めることでリラックスをし、眠りやすくなります。そのため、眠気を誘うので「運転前には飲まないでくださいね」と、注意書きされていますよね。
睡眠薬のようにあらゆる原因があっても眠れるようにする薬ではなく、「痛みや気持ちを鎮めること」で眠れる頭痛薬は「眠れない原因を分析する」のに、役立ちます。
分かりやすくまとめると、頭痛薬で眠れる理由は2つ。
①興奮や緊張、神経の高ぶりで眠れなくなっている。
②体の炎症反応からくる「痛み」や「不快感」から眠れなくなっている。
※炎症反応とは、ダメージから体を守る免疫反応で、痛みや不快感が出るものです。
頭痛薬を使うことで、「眠れない原因」をざっくり切り分けることができます。
原因が見えてくると、行動のモチベーションもあがるので、睡眠改善がしやすくなります。
でも、これだけだと「眠れない原因」がざっくりしすぎですよね。
より原因を深ぼって分析していくために、次の3パターンをお伝えします。
①アセトアミノフェンの頭痛薬で眠れる場合
②非ステロイド系抗炎症薬で眠れる場合
③頭痛薬で眠りやすさが変わらない場合
眠れない原因を見極める①「アセトアミノフェン」
アセトアミノフェンで眠れる場合、興奮や緊張などの神経の高ぶりや、ストレスや不安などが「眠れない原因」の可能性が高まります。
この場合は、リラックスを中心としたメンタルケアが睡眠改善につながります。アセトアミノフェンの鎮痛鎮静作用は、痛みがやわらぐだけではなく、感情の波を抑える効果があるためです。アセトアミノフェンと伝えていますが、鎮痛鎮静作用のある成分であれば、似た効果が期待できます。
アセトアミノフェンで眠れる場合は、「呼吸法やマインドフルネスなどでリラックス能力を高める」。または、「クラシック音楽やヒーリングミュージック、ラベンダーの香りを使う」などが眠れる方法として見えてきます。
また、リラックスは慣れないと、むしろ不安につながることもあるため、リラックスが苦手な人は少しずつリラックスに慣れていくことが大切です(リラクゼーション誘発性不安)
ちなみに抗炎症薬が入っていないものがおすすめです。
なぜかというと、抗炎症薬が入っているもので眠れた場合、「眠れない原因」が見極めにくいからです。
アセトアミノフェンが主成分で、抗炎症薬が入っていないものの有名どころは「カロナール」です。
ただ、ひょっとしたらバージョンによって違うかもしれないので、パッケージ裏の「成分」と「効果説明」を読んで判断しましょう。確実なのは、薬剤師さんに聞くことです。
※心配になったら薬剤師さんに聞くことはすべてに言えることなので、ここからは割愛しますね。
眠れない原因を見極める②「非ステロイド系抗炎症薬」
非ステロイド系抗炎症薬で眠れる場合、体のダメージを防御・回復するための炎症反応の痛みや不快感が「眠れない原因」である可能性が高まります。
炎症反応で眠れない場合は、「体質改善」をすることで眠りやすくなります。食事であれば、野菜を食べる、ポリフェノールや抗炎症サプリ系をとる、運動をする、ダイエットをするなどです。特に内臓脂肪が多いと炎症反応につながるので注意です。あとはリラックスのような一時的なものではなく、慢性的なストレスを減らしていくのがおすすめです。
非ステロイド系抗炎症薬の成分で有名どころは「イブプロフェン」「ロキソプロフェン」「アセチルサリチル酸」です。薬の効果説明には「痛みの発生を抑える」「炎症を抑える」などの、「痛みや炎症に効果がある」と書かれていることが多いです。ちなみに僕はイブを飲むことがあるんですが、イブだからといってイブプロフェンではないので注意をしてくださいね。
非ステロイド系抗炎症薬の場合は、鎮静成分が入っていてもOKです。
なぜというと、鎮静成分が入っている入っていないでは「眠れない原因を見極めることが難しい」からです。というのも、炎症の痛みが抑えられると、自然とリラックスしやすくなるからです。鎮静作用のおかげかどうかが判断しにくいんですよね。
眠れない原因を見極める③「頭痛薬では眠りやすさが変わらない」
頭痛薬で何も変わらない場合は、睡眠独特の「眠れない原因」の可能性が高まります。
大きな原因だと3つあります。
①睡眠リズムが崩れているなどの【体内時計】
②脳の睡眠欲求が足りていないなどの【睡眠圧】
③ベッドに入ると目が覚めるなどの【睡眠メタ認知】
それぞれ解決策を簡単にまとめると。
①体内時計:起床時刻を規則正しくし、朝から光をあびる。
②睡眠圧:日中の活動量を増やし、昼寝などの仮眠や横になる時間を減らす。
③睡眠メタ認知:眠ろう眠ろうとがんばらない。
今回は深ぼりませんが、この3つは「安定して回復する睡眠をとるためには必要」なので、整えていくことは大切です。「頭痛薬で眠りやすさが変わらない場合」だと、より重要性が高まります。
ここからは、今回お話した内容の注意点を伝えていきます。
頭痛薬で「眠れない原因」を見極めるときの注意点
①ウイルスや神経痛は睡眠とは別に改善する
今回は風邪などのウイルスや、坐骨神経痛・帯状疱疹などの神経痛は、除外しています。
それぞれ治してから、今回の方法をお使いください。
②無水カフェインが入っているものは注意
無水カフェインが入っていると、カフェイン効果で眠りにくくなります。今回の「眠れない原因を見極める」のが難しくなります。ただ、無水カフェインが入っているのに「頭痛薬で眠れる場合」は、カフェインの覚醒効果を上回って眠れています。カフェインは睡眠圧を妨害して目が覚めるため、睡眠の仕組みより、リラックスや体質改善の重要性が増します。
③頭痛薬で眠る習慣は作らない
頭痛薬は体への負担や副作用もあるため、特別な理由がない限りは毎日飲むなどは禁止。
④白か黒かで考えない
頭痛薬を使って、「眠れる・眠れない」ではなく「眠りやすくなるかどうか?」と、グラデーションで考えていくと、原因が見極めやすいです
「③頭痛薬で眠る習慣は作らない」と「④白か黒かで考えない」を深ぼってお伝えします。
「頭痛薬で眠る習慣をつくらない」
頭痛薬によって眠りやすくなる方もいると思います。でも、頭痛薬で眠る習慣は作らないでくださいね。今回はあくまで「眠れない原因を見極めるだけ」に使う提案です。
頭痛薬は、胃や腎臓や肝臓に負担があったり、アレルギーが出ることもあり、注意が必要です。特に高齢の方は気をつけましょう。アセトアミノフェンは比較的安全と言われますが、「他と比べて」というだけです。しかも、これは個人差があります。他にも「ロキソプロフェン」は即効性があり効果が高いですが、その分、副作用が出る可能性も高まるので注意です。
頭痛薬は「眠れない原因を見極めるだけに使うなど一時的に使って、習慣的に飲まないこと」です。
頭痛薬に頼らず「眠れない原因を解決」してきましょう。
「白か黒かで考えない」
睡眠に限らず、原因は白か黒かで、考えないことが大切です。
現実において「原因は明確になることはほとんどない」からです。80%、60%、30%みたいに部分的に原因を考えることが大切です。
そう考えた場合、「頭痛薬の眠りやすさ」は次のように分けられます。
①頭痛薬を飲むとすんなり眠れる。
②頭痛薬を飲むと眠りやすくなる。
③頭痛薬を飲んでも変わらない。
④頭痛薬を飲むとむしろ眠りにくくなる。
それぞれの「眠れない原因」をシンプルにまとめると
①②なら、アセトアミノフェンなら「リラックス系」、非ステロイド系抗炎症なら「体質改善」。
③なら、「体内時計・睡眠圧・睡眠メタ認知」。
④なら、「薬の副作用などに注意」、または「頭痛薬で眠れるかも?」という気持ちから睡眠への執着が生まれて眠れない「睡眠メタ認知」の可能性がでてきます。
原因が2つ以上あると考えて、可能性が高い原因から行動する
僕が悩みを解決していくときに使う方法が、今回のような「原因を絞り込む方法」です。
原因と考えられるものが10個ある場合、そこから1個を特定するのではなく、10個を6個に減らし、4個に減らし、2個に絞り込む方法をとります。こうして、原因を見極めて解決していきます。
なので、「これだけすればいい」という方法ではなく、「現実的に改善する方法のバランスをとっていく」考え方をします。おそらく不眠症と双極性障害を改善できているのは、「正解」ではなく「自分にとってどうであるか」を大切にしているからかな?と思っています。
先ほど、違和感がある言葉あったと思います。
「2個に絞り込む方法をとります」ですね。実は「原因を1つに特定することはしません」。どれだけ原因が見えても「他に原因があるかも?」と選択肢は残しておきます。
原因を1つに特定すると、うまくいかなかったときに絶望します。でも「自分には見えていない原因がある」と、1つ選択肢を残しておくことで、うまくいかなかったときに希望が持てます。これは「眠れない原因」のようにネガティブなものだけではなく、「眠れた理由」みたいなポジティブなものに対しても同じです。「正解に捉われないこと」が現実的に問題を解決するには大切です。
「原因が2つ以上あると考えて、可能性が高い原因から行動する」ですね。
この「あいまいさを含みながら、答えに向かうこと」がとても重要だと思っています。