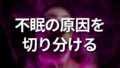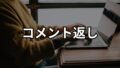体内時計が崩れると、睡眠以外にも問題が出ることを知っていますか?
体内時計が崩れると次の症状が出やすくなります
・不眠になりやすくなる
・中途覚醒、早朝覚醒、びくつき現象、悪夢などが起きやすくなる
・うつ症状が出やすくなる
・不安や反芻思考が強くなる
・イライラや悲しみなど感情が不安定になる
・太りすぎ、やせすぎ、疲れやすいなどの体の不調が出やすくなる
夜型になっていけば、寝つきが悪くなるなどの入眠時不眠症。
体内時計の崩れからノンレム睡眠やレム睡眠のパターンに歪みが出やすくなるので、中途覚醒や体がビクッとするびくつき現象や悪夢が起きやすくなります。
体内時計は睡眠のためだけではなくて、起きている時に元気に活動できるかどうかにも大きく関わっています。
そのため体内時計が崩れると、うつ症状や、不安や反芻思考、感情が不安定になるなどの症状も出やすくなります。
脳内ホルモンの影響から、食欲や代謝による問題が出やすくなるので、太りすぎ、やせすぎ、疲れやすいなどの、体の不調につながりやすくもなります。
体内時計が整うことで、覚醒と睡眠のリズムが整います。
日中は元気に活動的になり、夜はリラックスして眠りやすくなり、生活全体が向上していきます。
今日から体内時計をガチっと整えて、質の良い生活を手に入れていきませんか?
次の流れでお伝えします。
①体内時計の解説
②体内時計を整える全体の考え方
③朝から夜にかけての具体的な体内時計の整え方
④僕の体内時計の整え方
はじめから見ることで体内時計の整え方の理解がしやすくなります。
ただ、時間がない方はご興味があるところからご覧ください。
すべてを行おうと思うのではなく、「今はできていないけど、これはできそうだな」と思うところから行っていきましょう。
- 体内時計は1日の睡眠と覚醒のリズムを作る
- 不眠症の治りにくさは、症状の重さより、原因の複雑さ
- 自分の体内時計を知って、最適な生活リズムを見つける
- 起床時間と就寝時間を規則正しくすると、体と心も健康になる
- カロリー摂取時間を規則正しくすると、体内時計が整う
- 体内時計の整え方は深部体温で考えると分かりやすい
- 早寝早起きではなく、早起き早寝から始めるのが大事
- 目覚めを快適にする:夜明けシミュレーション
- 体内の親時計を整える最強の方法は「光」
- 朝の目覚めが1日で最も気持ちよくなる:自己覚醒
- 朝の温かいシャワーは要注意。朝の冷たいシャワーで体内時計が整う
- 体内時計を整える朝食は、インスリンとIGF-1がカギ
- 午前中の運動は、体内時計の子時計たちを整える
- 朝が弱い人は、モーニングルーティンで体内時計を整えよう
- カフェイン摂取は間違うと、翌日以降も体内時計が遅れ続ける
- 寝る前のアルコールは睡眠全体ではマイナス
- LEDで体内時計が崩れるのは、たくさんのブルーライトが隠れているから?
- 夜の運動と食事は、体内時計を夜型にする
- ぐっすり眠れるお風呂のカギは深部体温と自律神経
- 朝カフェイン・夜メラトニンサプリで体内時計が圧倒的に整う
- 朝に光を浴びることが、不正解になることもある:夜勤勤務の体内時計
- 僕が体内時計を整えるときの方法はコレだ
体内時計は1日の睡眠と覚醒のリズムを作る
体内時計は、僕たちの体の24時間周期のリズムです。これをサーカディアンリズムと呼びます。個人差はありますが、24時間よりも少し長めです。
ただ睡眠で困っている場合、生活リズムの影響で夜型になりやすくなるので、体内時計のリズムはより長くなってきます。
体内時計は睡眠だけではなく、覚醒やホルモンの分泌や体温をコントロールするなど、僕たちの脳や体を整える働きをしてくれます。
なので、睡眠に問題があるなし関わらず、体内時計を整えることはとても大事です。
体内時計の親時計と子時計はどこにある?
体内時計には親時計と子時計があります。
親時計は、子時計たちのタイミングをそろえていく体内時計の指揮者の役割を持っています。
目の奥のほうにある脳の視交叉上核にあります。
視交叉上核は、光の影響をとても強く受けるため、体内時計を整える時に最も効果があるのが光です。
光を浴びることによって、「今は朝だよ」と子時計たちに信号を送って、体が活動的になります。
夜になって光の量が減っていくと、体を休息モードに切り替えていきます。
子時計は、親時計のように1つではありません。
臓器や筋肉や皮膚などに、それぞれに子時計があります。
親時計が体内時計の指揮者であるならば、たくさんの子時計は演奏者ですね。
親時計の指揮をもとに、1日を過ごしていくための体全体のリズムを作っていきます。
光ほどの影響はありませんが、食事や運動や温度なども体内時計に影響を与えるのは、この子時計たちによるものですね。
この仕組みを知っておくと、体内時計の整え方が理解しやすくなります。
今回僕がお伝えする方法をそのまま使うだけではなく、工夫して行っていくことができるようになってきます。
ではまずは、睡眠全体から体内時計の重要性と整え方をお伝えしていきます。
不眠症の治りにくさは、症状の重さより、原因の複雑さ
不眠症や睡眠が崩れている場合、症状が重ければ重いほど治りにくいと思っていませんか?
不眠症の治りやすい・治りにくいというのは症状の重さよりも、原因が複雑かどうかというところが大切になってきます。
不眠症の原因が1つであれば、重い症状であったとしても、治す方法がとてもシンプルになってくるので治りやすいです。
例えば、体内時計の崩れのみが原因で、強い不眠症なのであれば、光と生活リズムを整えるだけで改善ができるからです。
逆に、不眠症の症状が軽くても、体内時計だけではなく、食物アレルギーや、肥満や、怪我や痛みや、完璧主義傾向など、あらゆる原因が重なっている場合は、原因が複雑になるので、治す方法も複雑になってきます。
睡眠を改善していく時に重要なのが、「体内時計、睡眠圧、睡眠認知」の3つです。
睡眠圧は、脳が求める睡眠の欲求の強さ。
睡眠認知は、脳が緊張や興奮をする考え方をしているかどうかというところです。
睡眠では、この3つの影響がとても強いので、まずはこの3つを整えていくことが大切です。
基本的に人は眠れるようにはなっているので、多少マイナスなことがあったとしても体内時計、睡眠圧、睡眠認知が整っていれば、不眠症状が続くことはありません。
ただ実際には、何が原因で不眠症になっているかというのは分かりにくいものです。
なので、体内時計、睡眠圧、睡眠認知をそれぞれ改善して原因を減らしていくことが大切です。
この中で最も改善しやすいのが「体内時計」です。
なぜなら体内時計は、基本的に「朝に光を浴びる、食べる、体を動かす、夜にその逆を行う」と言う風に、改善の仕方がとても分かりやすいからです。
では、どのように体内時計を整えていけばいいかをお伝えします。
自分の体内時計を知って、最適な生活リズムを見つける
自分の体内時計の状態を知っていますか?
体内時計を整えていく時に大切なのは、まずは現在の体内時計の状態を知ることです。
もしも現在あなたが夜型ではなく朝型なのであれば、体内時計は軽めに意識をして、睡眠圧や睡眠認知など別の原因に力を注ぐことが大切になってきます。
体内時計が整っているという状態は、体内時計と生活のリズムが合っているということです。
なので、一言で体内時計が整っていると言っても、人それぞれの生活リズムによって変わってきます。
あくまで一般的な社会の生活リズムが朝型が最適なだけでやって、夜勤勤務をしているなど生活リズムによっては、夜型の方が体内時計が整っていることもあります。
ただ、今の体内時計の状態を知らないと、どのように体内時計を整えていけばいいかも見えてこないので、体内時計の状態を知るために朝型夜型質問紙(MEQ)を一度行うことがおすすめです。
朝型夜型質問紙(MEQ)とは?
朝型夜型質問紙(MEQ)は、自分が朝型か夜型かを評価するための自己評価アンケートです。
あなたが現在どの時間帯に集中しやすいかが見えてくるものです。
体内時計を整える上ではとても役立ちます。
>朝型夜型質問紙(MEQ)
朝型夜型質問紙に答えると朝型か夜型かが分かってきます。
もともと持っている遺伝子タイプによっても、朝型になりやすいかどうかがあります。
なので、「朝型にする」というより「朝型に寄せていく」という考えがおすすめです。
ちなみに遺伝と環境だと、影響度はそれぞれ半分ぐらいです。
点数が出てきますがこれは意識しなくてOKです。
夜型になれば夜型になるほど、夜に集中しやすいタイプになってくるので、どうしても夜更かしをしやすくなってしまいます。
午前中から活動的に動いていくという意味では、朝型から中間型に入るぐらいがおすすめです。
超朝型で早朝覚醒に困っている場合は、体内時計を遅らせることも1つの方法です。
朝型夜型質問紙は睡眠クリニックや心療内科などの病院でも使われるほど信頼感が高いものです。
世界中の4,000回以上の研究で利用されています。安心して使ってみてくださいね。
起床時間と就寝時間を規則正しくすると、体と心も健康になる
起床時間と就寝時間を規則正しくする効果を知っていますか?
体内時計と聞くと、朝型か夜型かというところに意識が向くかもしれません。
でも、重要なのは、毎日の体内時計のリズムがズレていないかどうかです。
毎日の体内時計のリズムのズレがなければないほど、睡眠と覚醒のリズムが整います。
そのため、夜に眠りやすくなり、睡眠の質が上がります。中途覚醒や、びくつき現象や悪夢も減りやすくなります。レム睡眠やノンレム睡眠の睡眠パターンが安定してくるからです。
メンタルも安定し、日中の集中力も増してきます。
体内時計のリズムが、日によって違ってしまうと、睡眠だけではなく体と心に悪影響が出やすくなります。
例えば、平日は規則正しく就寝と起床しているんだけど、週末に夜更かしをして、休みの日に遅く起きてしまう場合、うつ症状や不安が強くなるなどの悪影響が出やすくなってきます。また体にも影響が出るので、疲労感や不快感が出てきます。
このように、平日と週末によって体内時計がずれてしまうことを社会的ジェットラグと呼びます。
平日と休日という社会的なリズムによって生まれる時差ボケのことです。
もちろん社会的なリズムに限らず、毎日起床時間がずれていると、同じ症状が出やすくなってきます。
起床時間は「どれくらいのズレであれば問題がないのか?」をまとめたものが次のものです。
理想:30分以内のズレ
問題なし:1時間以内
注意:1~2時間
危険:2時間以上
起床時間のズレが1時間以上ある日が増えると、心と体に悪影響が出やすくなります。
なので、早起きを始めるときには、いきなり1時間も2時間も早く起きようとすると、体調が悪くなりやすくなるので、要注意です。
もちろん継続していけば、体が慣れて安定はしてきます。
ただ、1〜2時間の早起きというのは、ただでさえハードルが高く感じる上に、体調まで悪くなってしまうと、早起きすることに挫折しやすくなります。
しかも、早起きに挫折して、また以前の起床時間に戻して、また早起きにチャレンジをするを繰り返すと、ずっとこの症状に悩まされてしまうことになるので、お気をつけください。
起床時間と就寝時間を規則正しくすることは大切ですが、無理のない範囲で行っていくことが大切です。
早起きを始める場合は、15~30分早くするぐらいにしておくことが大切です。
カロリー摂取時間を規則正しくすると、体内時計が整う
カロリー摂取のタイミングで体内時計が整うことを知っていますか?
体内時計を整える上で見落としがちなのが、カロリーの摂取時間です。
それぞれの臓器に体内時計の子時計があります。
光よりは影響は少ないんですが、食事は体内時計に影響を与えます。
そのため、朝ごはん、昼ごはん、晩ごはんを食べる時間帯が毎日ずれている人と、規則正しい人では、体内時計の整いやすさが変わってきます。
特に高いカロリーをとる3食の時間帯を規則正しくしていくことで、睡眠や健康が整いやすくなります。もちろん、2食の人は2食で整えてもOKです。
同じ理由で、おやつなどの間食も規則正しいリズムを作るのがおすすめです。
15時のおやつであるとか、夕食を食べた後でおやつを食べるであるとか、このように、リズムを作っておくと体内時計が整いやすくなります。
特に炭水化物とタンパク質は体内時計に影響を与えやすいと覚えておくと、工夫がしやすいです。
体内時計の整え方は深部体温で考えると分かりやすい
深部体温で考えると、体内時計を整える方法が見えてくることを知っていますか?
親時計である脳の視交叉上核が、それぞれの臓器に活動するタイミングを知らせるので、深部体温は体内時計とリズムが似てきます。
臓器の子時計も全体の体内時計に影響を与えるので、深部体温のリズムを整えると、全体の体内時計が整ってきます。
深部体温は臓器の体温と思っていただいてOKです。
深部体温は、朝から夕方にかけてまで上がっていき、その後は翌日の午前3時から4時ぐらいまで下がっていきます。
このリズムを知っておくと体内時計を整える方法が見えてきます。
次のように考えると、睡眠につながる体内時計の整え方が見えてきます。
・朝と昼は、深部体温が上がっていくことをする。
・夜は、深部体温が下がっていくことをする。
寝室は涼しい方がいい理由も、これだけで分かってきますね。
早寝早起きではなく、早起き早寝から始めるのが大事
体内時計を整えるには、早寝早起きではなく、早起き早寝が大切だと知っていますか?
体内時計を整えていく時には、起床時間と就寝時間を整えていくことが大切です。
毎日の体内時計のリズムのズレが少なければ少ないほど、睡眠とメンタルと体の調子が良くなっていくからです。
まずは「起床時間から整えていく」のが現実的です。
寝るというのはスイッチのように切り替えられるものではないので、コントロールがやや難しいからです。逆に、起きる方は、光や音、人の助けを借りるなど、自分以外の力によって、コントロールができます。
起床時間が整うと、自然と就寝時間も整ってきます。
早起きを始めるにしても15~30分ほどから早めていくことが大切です。
起床時間をいきなり大きくずらしてしまうと、うつ症状や感情が不安定になるなどの、時差ボケと似たような症状が出やすくなるからです。
1週間から10日ほどして慣れてきたら、また15~30分早めていくという風に「少しずつ早起きにしていく」と、健康的な体調のまま早起き習慣が無理なくついていきます。
無理して1~2時間早く起きようとすると、体調が崩れやすくなってしまい、早起きを続けにくくなるので注意をしてくださいね。
一般的な社会リズムで考えると、起床は朝6〜8時ぐらいがおすすめです。
朝日が出ている時間帯に起きるほうが体内時計を整えやすくなるからです。
早起きをしたら、できるだけ早めに光を浴びて体内時計の親時計を動かす。
水を飲んで、臓器にある子時計を動かす。
こうすることで早起きでの体内時計のリズムができてきます。
目覚めを快適にする:夜明けシミュレーション
起きる前から、光をあびることで、快適な目覚めにつながることを知っていますか?
体内時計を整える方法で、朝の目覚めがよくなる方法が「夜明けシミュレーション」です。
その名の通り、夜明けをシミュレーションするものです。
体内時計が崩れている人だけではなく、朝目覚めるのが苦手な方や、太陽が上がっている時間が短い地域に住んでいる方や、季節性うつ病の方におすすめです。
季節性うつ病というのは、太陽が上がっている時間が短くなる冬などにうつ病が悪化しやすいうつ病です。
目覚める前から、光を浴びることによって、脳は「朝が来た」と判断します。
そうすることで、抗ストレスホルモンであるコルチゾールが目覚めをサポートしてくれて、自然な目覚めに繋がりやすくなります。
具体的な方法としては「光目覚まし時計を使う」がおすすめです。
音が鳴る時計とは違って、少しずつ明るくなっていく目覚まし時計ですね。
光によって体が目覚める準備をしてくれるので、自然な目覚めにつながってきます。
自然な目覚めに繋がってくると、朝起きた時の寝ぼけ感(睡眠慣性)や不快感がなく、心地よい目覚めになります。
これは自然に目覚める自己覚醒の作用によるものです。
カーテンを少し開けて眠る方法もあります。
ただ、カーテンを少し開けて眠る場合は、季節によって光が早めに入り始めたり、遅めに入り始めるなど、自分が望む起床時間のコントロールがやや難しくなることがあります。
他にも寝室や住んでいる場所の関係で難しいこともあります。
夜明けシミュレーションと呼ばれている通り、少しずつ明るくなっていくところがポイントです。
急に明るい光を浴びると、びっくりして目覚めてしまうので、目覚めが悪くなることがあります。さらに昼ぐらいまでモチベーションが上がりにくいこともあります。これは目覚めの準備ができずに目覚めてしまったり、急な光の刺激で交感神経が高ぶってしまうためです。
アイマスクをしていて、朝目覚める時までアイマスクが外れていない場合は、この夜明けシミュレーションの効果が得られないので、目覚めが悪くなる可能性があります。
この辺りは実際試してみての判断ですね。
体内の親時計を整える最強の方法は「光」
体内時計をリセットするには、いつ・どのくらいの光を浴びればいいか知っていますか?
体内時計を整えていくためには、光が最も効果が高いです。
これは体内時計の親時計がある視交叉上核が光に影響を受けるからです。
他にも光は気分の改善効果や、睡眠を維持する力が高まる効果があると2023年の光療法の研究で報告されています。
体内時計を整えるには、いかに光を浴びるかが最大の鍵です。
▼体内時計を整える光のタイミング
理想:起床後30分以内に浴びる
優秀:起床後1時間以内に浴びる
良好:午前中に浴びる
普通:夕方までに浴びる
悪い:夕方以降に浴びる
体内時計を整える意味では、午前中に強い光を浴びておく必要です。
ただ、睡眠維持をする力が高まるという意味では、夕方までであれば良い効果が期待できます。
夕方以降に強い光を浴びると、体内時計が夜型になっていきます。
では、強い光とは、どのくらいの光なのかと言うと、2,500ルクス以上の光です。先ほどのフランスの研究では2,000ルクス以上としていますね。
基本的に部屋の明かりは1,000ルクス以下になるので、外で太陽の光を浴びるか、セラピーライトなどの専用の装置の光を浴びる必要があります。
曇りの場合でも、2,500ルクスは超えていることが多いので、曇りの日でも外の光を浴びることは大切です。
ただ、曇りの場合は「どれだけ曇っているか?」にもよってくきます。
安定的に体内時計を整えるためにはセラピーライトなどの光療法の装置があると便利です。
気分改善効果などを考えると、外で30分以上の光を浴びるのがおすすめです。最低でも外で15分以上は光をあびましょう。
僕の場合は起床後、30分以内に、近くの大きな川まで自転車で移動して帰ってきています。軽めに運動もするので30〜40分過ごしていますね。
また、目覚める前から少しずつ明るくなっていく光を浴びる夜明けシミュレーションも、目覚めにいい効果があります。
▶高照度の光を放つ:12000lux フルスペクトル LED 光 目覚まし体内時計 がリセット
朝の目覚めが1日で最も気持ちよくなる:自己覚醒
気持ちよく朝目覚めるには、大きな音が鳴る目覚まし時計は使わない方がいいと知っていますか?
朝、気持ちよく目覚めるには、自己覚醒で目覚めることが大切です。
自己覚醒というのは、外のサポートを借りずに自然と目覚めることです。
自然に目覚めるので、すっきりと心地よく目覚めやすくなります。
寝ぼけ感も少ないので、目覚めて5分で活動ができるようになります。
大きな音などで急に目覚めると、ノンレム睡眠やレム睡眠という睡眠段階の途中で目覚めてしまい、頭がぼーっとしたり、ネガティブな気持ちになりやすくなるので注意です。
自己覚醒で目覚めるには、起床時間を規則正しくすることです。
何時に起きればいいか、体が体内時計によって覚えてくれるので、自然といつも同じ時間に目覚めやすくなります。
例えば、普段6時に二度寝もせずに目覚めている場合、6時少し前に自然と目覚めることがあります。これは自己覚醒によるものです。
他にも、自己覚醒で目覚めるためには、自然に近い形で目覚めることが大切です。
目覚める前から少しずつ光を当てていく「夜明けシミュレーション」。
体がびっくりしない自然に近いレベルの音や振動で目覚める。
具体的には、小さな自然音やメロディーで目覚めたり、スマホや時計のバイブ機能で目覚めるなどです。
僕の場合、大きなアラームで目覚めていたときは、二度寝がしたくなるくらいに、起床はしんどいものでした。目覚めがとても不快だったんですね。
でも、自己覚醒で目覚めると、朝の目覚めが1日の中でも最も気持ちいいぐらいに感じるようになりました。
朝の温かいシャワーは要注意。朝の冷たいシャワーで体内時計が整う
朝の冷水シャワーに体内時計を整える効果があると知っていますか?
体内時計は、脳にある親時計と臓器などにある子時計があります。
冷水シャワーは体の表面を冷やすことで、体の中の温度を高めるので、たくさんの子時計を整える効果があります。
冷水シャワーには
・交感神経を高める。
・血行を良くする。
・自律神経を整える(副交感神経も活性化するため)。
などの効果もあるので、自然と朝から昼にかけて活動的に動きやすくもなります。朝から元気に活動的に過ごして、体内時計を整えていくにはかなり効果が高い方法です。
シャキっと目覚めるので、朝弱い方におすすめですね。
具体的には、30秒以上冷たいシャワーを浴びるだけでOKです。
気分をよりスッキリしたい場合は首の裏に冷水を当てることをおすすめします。首の裏には、副交感神経の約75%がある迷走神経が集まっているので、強いリラックス効果があるためです。
副交感神経による強いリラックス効果と、冷たい刺激による交感神経の活性化にあるので、爽快感があります。
ただ、心臓や体がとても弱い方はやめたほうがいいです。心臓に負担がかかるためです。
朝の温かいシャワーについてはマイナスに働く可能性があるので要注意です。
体の表面を温めることで、体が深部体温が下げて、眠気を誘うリラックスにつながるからです。
睡眠で固くなった体を温かいシャワーでほぐして、その後活動的に動くという風に使えば問題はありません。
温かいシャワーを浴びる場合は、最後に冷たいシャワーで締めるのがおすすめです。
体内時計を整える朝食は、インスリンとIGF-1がカギ
炭水化物とタンパク質に体内時計を整える効果があると知っていますか?
体内時計を整える上では朝食を食べることは大切です。
臓器に体内時計の子時計があるので、光ほどではないですが体内時計を整える効果があるからです。あと、しっかりと噛むことによって顎などの刺激で体も活性化されていきます。
朝ごはんでは、特に炭水化物とタンパク質が大切です。
炭水化物を取ると、インスリンが分泌されます。このインスリンは体内時計をリセットする力があります。
また、タンパク質を取るとIGF-1という物質がインスリンと似たような働きによって体内時計を整える効果が出てきます。
朝から炭水化物とタンパク質をとることによって、活動的に動いても疲労がたまりにくくもなります。
ただ、血糖値が上がりすぎてしまうと、けだるくなって活動的に動けない場合もあるので、朝食の量は個人個人にあった量にすることが大切です。
炭水化物とタンパク質を考えた上で、朝の少ない時間でさらっと食べられるという意味では、バナナヨーグルトや卵かけご飯や納豆ご飯というのは、朝ごはんにはかなり適していると思います。
僕の場合は炭水化物が多めに入ったプロテインを飲むようにしています。
カロリー制限や断食は、体を健康にする上では良いメリットもありますが、体内時計を整えていく上ではマイナスに働きやすくなります。
体内時計が崩れていて、なかなか調子が上がらない、寝つきが悪いなどの場合は、朝ごはんを抜くなどの断食はやめることをおすすめします。
午前中の運動は、体内時計の子時計たちを整える
午前中の運動が体内時計を整えることを知っていますか?
午前中の運動は体内時計を整える上では効果がとても高いです。
運動は深部体温を高めて、臓器などにある体内時計の子時計たちに「朝だ」と言うスイッチが入りやすくなるからです。
慢性的な疲労を抱えている人にも午前中の運動はおすすめです。
朝から活動的に体が動くことで、体全体に血が巡るので脳も体も動きやすくなってきます。
そうなると、全身のこりや血行不良による疲れが薄れていきます。さらに、血液が回ることで、体全体の回復にもつながってきます。
特に現代は、体を動かさない血行不良によって疲れている人が多いので、午前中の運動はとてもおすすめです。
もちろん体力がついて健康的な体にもなっていくので、深く眠りやすくなって、睡眠の質も高まってきます。
定番としておすすめなのが「朝のウォーキング」です。
光と運動を両方取り入れることができるので、体内時計を整える効果はとても高いです。
もちろんジョギングも効果は高いですが、慣れた方でないとジョギングは肉体的な負荷が高いので、疲れが出て日中の活動量が下がる可能性もあります。この辺りは個人差ですね。
運動レベルは「楽しく会話ができる」ぐらいの運動がおすすめです。これはRPEという主観的に運動レベルを計るときに使う考え方の1つです。
他にも、体をほぐすような動的ストレッチや、ラジオ体操のような全身運動も睡眠中で硬くなった筋肉をほぐして、1日を活動的に過ごしていくにはおすすめです。
光の影響も合わせて考えると、理想としては外で30分の運動ができると、睡眠も体も心もいい方向に向かってきます。
家で運動する場合は窓を開けて光を取り入れながら、行うのが効果的です。
僕の場合は一時期ラジオ体操を取り入れたことがあります。
子供のころは、手を抜いてやっていたのでよくわからなかったんですが、しっかり行うと体全体をバランスよく整える運動としてはとても効果が高いです。
朝が弱い人は、モーニングルーティンで体内時計を整えよう
起床後の朝の習慣を作ることが大切と知っていますか?
目覚めた後の朝の習慣を作るのはとても大切です。
体内時計が整っていない場合は、朝の目覚めが悪かったり、頭がうまく働かずに、ぼーっとしてしまうことというのが多いですからです。
でも、体内時計を整えていくには、光を浴びる、運動や食事をする、他にも体を活動的に動かすために「顔を洗う」や「水を飲む」や「シャワー浴びる」など、朝から活動的に動くことが大切です。
でも、頭がぼーっとしていて、体がだるいと、「窓を開けて光を浴びる」なども面倒でできないことがあります。
そんな時に力になるのが「朝の行動の習慣化」です。
モーニングルーティンという言い方もしますね。
習慣化された行動は、あまり気力がない時でもできます。
朝目覚めたあとのように、頭や体が動きにくいときには、習慣の力を借りると行動が簡単になります。
起床後にどんな行動をするかを決めておくと、行動しやすくもなります。
何をするか悩まなくなるからです。
カーテン開けて光浴びようか、それとも着替えようか、二度寝しようか、どうしようか、という風に悩んでしまうと人は普段の行動をとりやすくなります。人は基本的に現状維持の心理が働くためです。
二度寝を普段している人は二度寝をするし、ベッドでゴロゴロしている人はベッドでゴロゴロします。
なので体内時計を整えるために目覚めた後の行動を変えるには、何をするかを決めておくというのはとても大切です。
はじめて朝の習慣を作るときは
①カーテンを開ける
②水を飲む
③顔洗う
という、3つぐらいの簡単で効果がある行動がおすすめです。
行動が多すぎてしまうと「何からすればいいんだっけ?」と結局悩んでしまって行動しなくなる可能性があがります。
また、習慣化するまである程度日数もかかってしまうので、できるだけ簡単にできる行動習慣から付けていくのが大切です。
少しずつ朝の行動習慣がついてきたら、今回のご紹介している方法を参考にレベルアップしていきましょう。
ロンドン大学のフィリッパラリー博士によると、人の行動が習慣化するまで18~254日とのことです。
簡単な行動ほど習慣化はされやすくなってきます。
先ほどのカーテンを開ける、水を飲む、顔洗うという3つの簡単な行動であれば、3週間ほどで身に付く可能性が高いです。
また、ハーバードビジネススクールの2016年の調査によると、習慣化された行動をとることによって、不安感が和らぐことが分かっています。
つまり、モーニングルーティンを持つことは、仕事や学校に対するストレスを減らし、快適に朝から行動することにつながります。
カフェイン摂取は間違うと、翌日以降も体内時計が遅れ続ける
カフェインは間違った取り方をすると、体内時計のパターンそのものを遅らせてしまうと知っていますか?
カフェインは覚醒作用があって、適切なタイミングでとると、集中力やパフォーマンスを上げる良い効果があります。
でも、カフェインをとりすぎてしまったり、遅く取ってしまうと、体内時計を遅らせてしまい、睡眠に悪い影響が出てくることがあります。
カフェインを取るおすすめのタイミングとしては、「起床してから2時間以上、午後2時まで」です。
起床後は、体を自然と目覚めさせるためにコルチゾールなどのホルモンがサポートしてくれます。
自然な覚醒が30~60分ほど促されるので、それが終わった後で日中の活動力を上げるためにコーヒーなどでカフェインを取っていくのが適切な方法です。起床時間にもよりますが、10時から14時にカフェインを取るぐらいが目安になります。
起床後すぐにコーヒーなどでカフェインを取ってしまうと、カフェインによる目覚めの効果も合わさって、体に負荷がかかってしまって、疲れやすさが出ることがあるので注意です。
カフェインの効果が持続する時間は、半減期を考えると4~8時間と言われています。
そのため、22時に寝る場合であれば14時にはカフェインをやめておきたいところです。
ただ、カフェインに対する感受性や耐性などによって効果の持続時間は変わってくるので、個人差はあります。
カフェインの推奨上限量は、1日400mgまでです。コーヒーの場合は3~4杯です。
もちろん、コーヒーの種類やカップの大きさ、カフェインの感受性や耐性などの体質によっても変わってきます。
カフェインを安全に取り入れていくと考えると、100~200mg。コーヒーなら1~2杯ぐらいを目安にするのがおすすめです。
アメリカコロラド大学の体内時計とカフェインの研究では、就寝時刻の3時間前にWエスプレッソを1杯分に相当するカフェインを取ると、体内時計のパターンが40分遅れたと報告しています。
体内時計のパターンが遅れてしまうので、翌日以降も体内時計が遅れてしまいます。
体内時計を考える上では、夕方以降のカフェインはやめることが大切です。
寝る前のアルコールは睡眠全体ではマイナス
寝る前にアルコールを飲むことが、体内時計に悪影響を与えることを知っていますか?
アルコールは睡眠ホルモンと呼ばれるメラトニンを抑えてしまうので、結果的に体内時計が崩れやすくなります。
しかも、メラトニンが抑えられてしまうので、睡眠の質も下がりやすくなります。
寝る前のアルコールは、リラックス効果によって、寝つきが良くなることはあります。でも、睡眠全体においては強いマイナスに働きやすいです。
寝る前にアルコールを飲むことによって、体内でアルコールが分解されます。このときに有害な物質であるアセトアルデヒドが生まれ、体にストレスを与えます。そのため、睡眠の質が下がったり中途覚醒につながりやすくなります。
利尿作用があるのも中途覚醒につながる原因ですね。
また、アルコールを飲むことで、鼻の奥の血管が膨れ上がることによって、呼吸が浅くなったり、無呼吸症状が出やすくなります。
お酒を飲むといびきをしやすくなるのも、これが理由の1つですね。
脳に酸素があまり行かなくなると、睡眠による回復力が下がり、翌日のパフォーマンスがさがりやすくなります。
アルコールは自律神経を乱すので、睡眠だけではなく心と体ともにマイナスに働きやすいです。
睡眠のためには、アルコールは就寝の3~4時間前までには飲み終えることが大切です。
ただ、お酒によって人生の満足度を高めている方もいらっしゃるとは思います。
その場合は、「質のいい睡眠」と「アルコール」と、どちらが自分のとって大切か、というところで判断していただければと思います。
お酒を楽しみながら、睡眠もしっかり質を高めていきたい場合は、休日の昼や夕方などの食事で楽しむのがおすすめです。
例えば、休日の昼から行う花見やバーベキューや食事会などですね。
LEDで体内時計が崩れるのは、たくさんのブルーライトが隠れているから?
ブルーライトは色だけでは判断できないと知っていますか?
夜に光を浴びると体内時計は遅れてしまい、夜型になりやすくなります。
そのため、夜は光を減らしていくことが大切です。
特に就寝の1~2時間前には生活を崩さない範囲で光をなくしていきましょう。
午前中の光は体内時計を早める、夜の光は体内時計を遅らせると覚えておくと、分かりやすいと思います。
スマホの光ぐらいであれば、睡眠には影響しないと言われることもありますが、実際にはスマホぐらいの小さな光でも少し睡眠に影響を与えます。
スマホは情報の刺激などもあるので寝る前は控えていくことが大切です。
夜のブルーライトは睡眠に良くないと聞いたことがありますよね。
ブルーライトと聞くと、青い光のイメージがあると思います。
青い光がNGで、光が赤くなっていくほど影響が薄れていくのが一般的な光の考え方です。
でも、この光の色によって判断できるのは、自然の光の場合です。人工の光の場合は考え方が変わります。
実際は、青い光が睡眠に悪いのではなくて、短い波長の光が睡眠に悪いんです。
人工の光の場合は、光に色をつけることができるので、見た目の色に関わらず、波長の短いブルーライトが含まれている可能性があります。
例えば、照明器具は人工の光なので色だけでは判断しにくいところがあります。特にLEDですね。
たまにLEDの光が苦手な方がいらっしゃいますが、ひょっとしたらブルーライトが多く含まれたLEDを使っているかもしれません。
もしも、ブルーライトを気にされる場合は、照明器具を買う時にブルーライト成分や波長スペクトルが書かれたものを選ぶことをおすすめします。
ただ、1つ1つ光の波長まで考えて照明器具を買うと、お金もかかるしめんどくさいと思います。
なので、最も手軽に夜の光で睡眠を悪くしない方法は、光の明るさを抑えることです。
ブルーライトカットができるメガネも手軽なので、ブルーライトカット99.9%のメガネのリンクを概要欄に載せておきます。
黒いメガネやオレンジのメガネに、ブルーライトカットがあると、光を抑えながら、ブルーライトの影響を減らすことができます。
夜の運動と食事は、体内時計を夜型にする
夜遅くの運動や食事が体内時計を遅らせることを知っていますか?
午前中に運動や食事をしっかりすると、体内時計が朝型になっていき、整ってきます。
でも、夜遅くに運動や食事をしっかりすると、体内時計が遅れてしまって夜型になりやすくなります。
光もそうですが、体内時計を整えるために「朝に良いこと」は、「夜遅い時間では基本はマイナスに働く」と覚えておくと、分かりやすいと思います。
基本的には、寝る2~3時間前までには運動や食事を終わらせておくことが大切です。
運動の場合は、体をほぐす動的ストレッチやヨガなどは深部体温を高めずにリラックスするのでOKです。
息が弾んだり、体が温かくなってくるレベルの運動は寝る前は控えた方がいいです。
体をぐいっと伸ばす一般的な静的ストレッチは適切に行わないと痛気持ちいいレベルになることが多く、睡眠にマイナスになりやすいのでお気をつけください。
体がほぐれるというリラックス感であれば問題ありません。でも、痛気持ちいいぐらいまで伸ばしてしまうと、体が活動的になってしまい睡眠に悪影響がでてきます。
痛気持ちいいというのは、リラックスではなくて、ドーパミンなどが出ている快感的な気持ちよさになってきます。
これは、リラックスをする副交感神経ではなくて、緊張や興奮につながる交感神経が働きやすくなります。
そのため、「寝る前にストレッチがいいよ」という話も、理屈が分かっていないとマイナスに働くことがあります。
寝る前のストレッチについては、「体」よりも「呼吸」や「気持ちの落ち着き」に意識を向けると、適切なストレッチがしやすくなります。
個人的には、ストレッチよりも、呼吸法や漸進的な筋弛緩法、ヨガや瞑想がおすすめです。
食事の場合は、寝る前に炭水化物を取ることによって、眠りやすくなる方もいます。
その場合もがっつり食べるのではなくて、フルーツをひとかけら食べるとか、少しだけ体に入れて眠りやすくするぐらいがおすすめです。
たくさん食べすぎてしまうと、体内時計に悪影響がでて、睡眠が崩れやすくなります。
ぐっすり眠れるお風呂のカギは深部体温と自律神経
寝る前にお風呂に入ることによってリラックスしてぐっすり眠ることができるという話はよく聞きますよね。
お風呂に入ってぐっすり眠れる理由は、体が温まってリラックスすることと、高まった体温を下げる働きが生まれ、深部体温が下がっていくからです。
なので、眠る前のお風呂は体の芯まで温めすぎないことが大切です。
お風呂の温度、入るタイミング、お風呂の時間は次を参考にしてください。
テキサス大学の2019年の研究(メタ分析)
お風呂の温度と時間
温度:40~42.5°C
時間:就寝の 1~2時間前 に 10分間
入眠時間(SOL)が短縮 され、睡眠の質(主観評価)や睡眠効率(SE)が向上
お風呂の温度については人によって感じ方が違うので、注意が必要です。
就寝の2時間以上前であれば、お風呂の温度はそれほど気にしなくて良いです。
でも、就寝の90分以内になってくると、「熱い」と感じてしまうレベルは交感神経が優位になって、眠りにくくなる可能性があるのでお気を付けください。
僕の場合であれば、寝る1時間前ぐらいなら、最近は39度ぐらいで、15分ぐらいがちょうどいいです。39度でも30分入ってしまうと、体の芯まで温まってきてしまって、寝るまでに熱が下がりきらずに寝つきが悪くなることがあります。
就寝の60分以内などの場合は、体の表面を温めるぐらいがおすすめです。
38度ぐらいと緩めにするか、お風呂に浸かる時間を減らすか、シャワーでささっと体の表面を温めるかですね。
そうすることで、体がほぐれる。体の表面を冷ますために深部体温が下がっていくという流れが生まれます。
時間や体温を考えると、就寝前60分以内はシャワーが良いと思います。
ポイントとしては、「寝る時に体が火照って熱いのではなく、体の温度が下がって冷めてきていること」です。
ここを意識しながら、お風呂のタイミングや時間を考えると、あなたにあった睡眠に良いお風呂につながってきます。
自律神経や熱に対する感受性の影響もあるので、個人差があります。なので、「この温度のお風呂が良い」とは言いにくいものなんですね。
朝カフェイン・夜メラトニンサプリで体内時計が圧倒的に整う
体内時計を圧倒的に整えませんか?
サプリメントを使った体内時計w整える方法があります。
それはカフェインとメラトニンを使うことです。
カフェインとメラトニンを適切なタイミングで取ることによって、体内時計を圧倒的に整えることができます。
カフェインは早い時間に飲むことによって、脳に覚醒を促して、1日を活動的に過ごすための力となります。そのため、結果的に体内時計が整えやすくなります。
ただ、カフェインを取りすぎてしまったり、遅めに取ってしまうと、体内時計がむしろ乱れてしまう可能性もあるので、注意が必要です。
起床後は、体を自然と目覚めさせるためにコルチゾールなどのホルモンが30~60分ほどサポートしてくれます。
この自然な目覚めが終わった後で日中の活動力を上げるためにコーヒーなどでカフェインを取っていくのが適切です。
自然な覚醒に余裕を持たせるため、「起床の2時間以降で就寝の8時間前までがカフェインの良いタイミング」です。
個人の生活リズムによりますが、10〜14時ぐらいですね。
昼寝をする方は、昼寝前に飲むと寝起きがすっきり目覚められるので、昼寝前が良いかもしれません。
カフェインの推奨上限量は、1日400mgまでです。コーヒーの場合は3~4杯です。
もちろん、コーヒーの種類やカップの大きさ、カフェインの感受性や耐性などの体質によっても変わってきます。
カフェインを安全に取り入れていくと考えると、100~200mg。コーヒーなら1~2杯ぐらいを目安にするのがおすすめです。
メラトニンサプリは、体内時計を夜モードにして、リラックスを促して眠りやすくするサプリです。
日本では、薬に分類されるので国内の店舗からは購入はできません。
サプリメントとして購入するには、海外輸入のiHerbなどを使って購入する流れとなります。
▶iHerbのメラトニンサプリ
体内時計に働きかけて自然な眠りを促すので、体内時計を整えるのに使えます。
メラトニンサプリを飲むタイミングは「決めた就寝時間の30~60分前に飲む」のがおすすめです。
体内時計に働きかけるので、できる限り同じ時間帯に飲むことが大切です。
メラトニンを飲む時間をバラバラにしてしまうと、体内時計にズレが生まれて、中途覚醒や悪夢など睡眠にマイナスにつながることがあるのでご注意ください。
飲む量は睡眠薬であればお医者さんに判断を仰ぎ、サプリメントで購入する場合は推奨量を意識しながら、少量から始めるのがおすすめです。
目覚めた後、眠気が残るようであれば、減らしていきましょう。
カフェインで覚醒をうながし、メラトニンで夜に自然と眠りやすくすることで、圧倒的に体内時計が整いやすくなります。
朝に光を浴びることが、不正解になることもある:夜勤勤務の体内時計
朝に光を浴びることが必ずしも大切ではないとご存知ですか?
夜勤勤務をしている方など、一般的な社会リズムと違う生活リズムを持っている方は、体内時計の整え方の考え方が変わってきます。
体内時計が整うというのは、「体内時計」と「生活のリズム」が合っているという意味だからです。
なので、正確には「朝に光を浴びる」ではなく、「自分の生活がスタートするところで光を浴びていくことが大切」です。
同じように生活リズムの終わりに近づいていくにつれて、光を抑えていくという流れになります。
一般的な社会リズムと違う生活リズムを送っている方は、光や食事や運動などの体内時計を整える意識は、より強く持っておく必要があります。
生活リズムに合わせて体内時計を整えようと思っても、太陽の時間を変えることができないので、どうしても朝や昼には光を浴びやすくなる、夜には光を浴びにくくなるからです。
セラピーライトなどの強い光を浴びられるアイテムを用意して、適切な体内時計と生活リズムのパターンを作っていくことが大切です。
24時間交代勤務の方は、自分でシフトがコントロールできる場合は、朝と夜を頻繁に入れ替えるのではなくて、連続して朝勤務を続ける、連続して夜勤務を続ける、その間に休日を入れてそこで体内時計を切り替えていくのが、適切な方法になります。
夜勤勤務や一般的な社会リズムと違う生活リズムを送っている方は、セラピーライトをどうぞ。
僕が体内時計を整えるときの方法はコレだ
たまに睡眠実験と考えて、生活リズムを変えていることがあります。
知識は使わないと、人に伝えるのが難しいのと、好奇心からです。
何度か試したんですが、やっぱり朝型から夜型にするより、夜型から朝型にするほうが時間は少しかかります。
では、僕の体内時計の整え方をお伝えします。
夜型から朝型に向けて整えるときの方法です。
朝型から夜型に変えたい人は、夜活動するだけでOKです。
①起床時間と就寝時間の目標を決める
現在は、朝6:30。夜は23:00。夜更かししても、起床時間は守る。
②朝、自転車で近くの大きな川へ行く。運動など含めて40分ぐらい
③帰宅後、冷水シャワーを30~60秒浴びる
④タンパク質と炭水化物をとる(運動中と帰宅後)
⑤朝型に素早くするときはカフェインのサプリ
※これが約1時間ぐらいのルーティン。
※この朝ルーティンがあれば、体内時計は整う。
毎日、約1時間のルーティンは大変そう見えるけど、効果が高いです。
・朝から体が活性化するので、日中の行動量も自然と増える。
・朝に運動することで、夜はほどよい疲れでリラックスできる。
・1日にメリハリがつくので、充実感がある
・1日の運動もこのときにほぼ終わらせることが多い