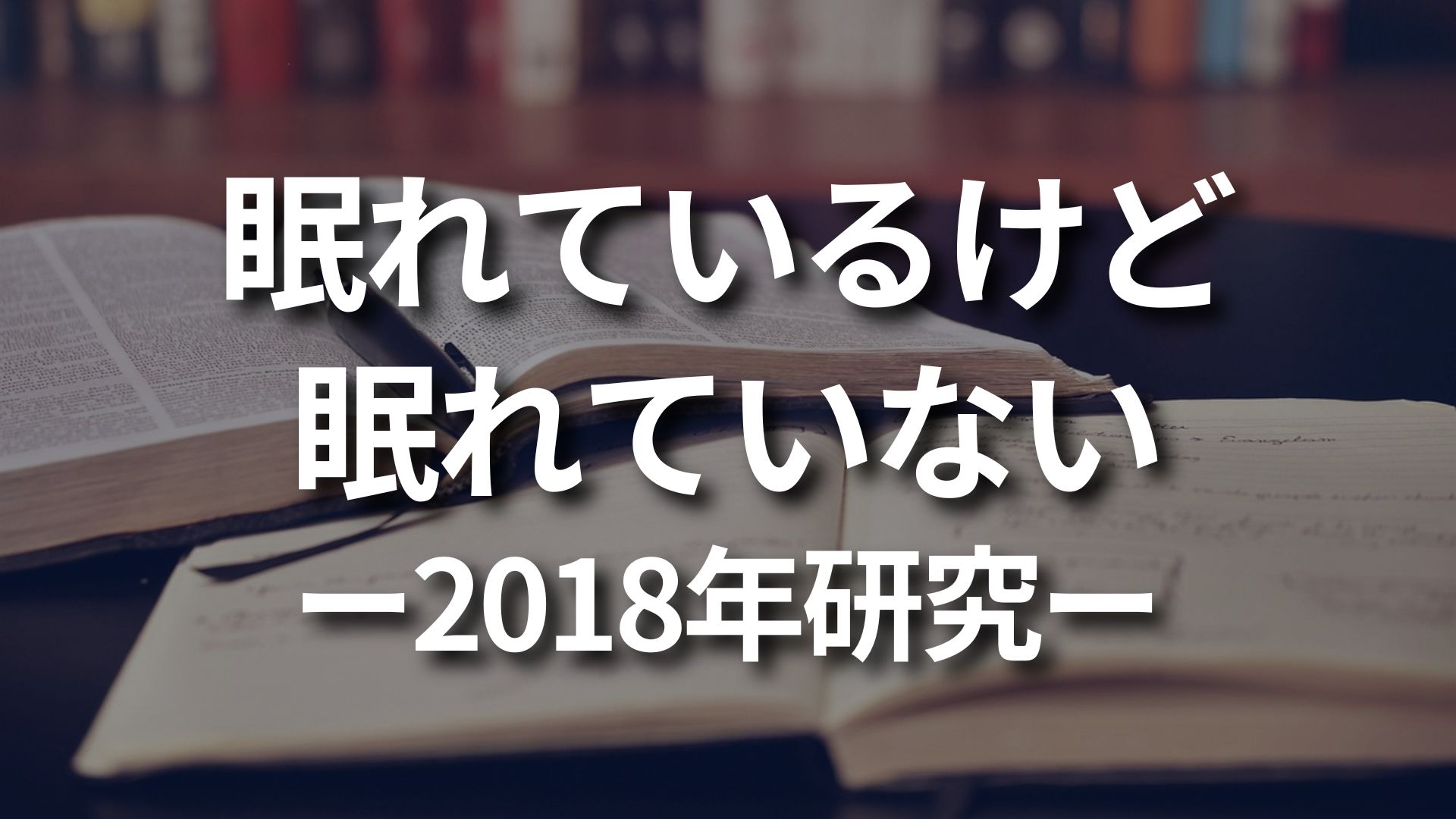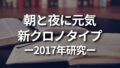逆説的不眠症とは、睡眠しているにもかかわらず「眠れていない」と感じる不眠症の一種です。
そのため、睡眠の主観的評価と客観的評価が一致しない点が特徴であり、その定義や診断基準には多くの議論が存在します。
最新の研究(カステルノヴォら、2019)では、この曖昧さを解消するために、既存の研究データを整理・分析し、統一的な診断基準を模索しました。
参考:逆説的不眠症のパラドックス:統一的な証拠に基づく定義に向けた理論的検討
【研究や論文は、chatGPTに著作権に配慮して、要点をまとめてもらっています。[ ]のメモは僕の意見・感想です】
結論
逆説的不眠症は、睡眠していると客観的に観測されているにもかかわらず、本人が「眠れていない」と感じる状態を指します。
今回の研究では、異なる診断基準を使用した場合、有病率が8%から66%と大きく異なる結果が得られました。
また、診断基準ごとの一致率も-0.19から0.9というばらつきが見られ、診断基準が統一されていないことが改めて浮き彫りになりました。
これにより、診断基準の標準化が急務であることが確認されました。
睡眠は主観的睡眠と客観的睡眠を分けて考えたほうが良いですよね。
睡眠法が共通しているところもあれば、主観か客観かで方法の優先順位が変わることもある。
ちなみに、客観的に眠れているからOKではなく、どちらも「眠れていること」が大事。なんとなく「主観的」て軽く見られがちな印象です。
内容の信頼性:8/10
本研究は、200名の慢性原発性不眠症患者と200名の健康者を対象に、MATLABを用いたデータ分析を行っています。
数値の信頼性が高く、研究手法も厳密であるため、学術的信頼性は高いと評価できます。
ただし、逆説的不眠症そのものの定義がまだ確立されていないため、診断基準に依存した結果の解釈には一定の注意が必要です。
慢性原発性不眠症患者は、純粋な慢性的な不眠症のことです。
身体的、精神的には原因がないけど、不眠症が3か月以上続くもの。
何の研究か?
逆説的不眠症の定義を統一し、その診断基準を確立するための理論的検討を目的とした研究です。
具体的には、19種類の異なる定量的定義を整理し、異なるデータセットに適用して検証を行いました。
対象データは、不眠症患者200名と健康者200名の睡眠パラメータを含んでいます。
このデータを分析し、診断基準の有効性と一致率を評価しました。
研究した理由は?
逆説的不眠症は、主観的評価と客観的評価が食い違うため、不眠症の中でも特に診断が難しいとされています。
これまでも逆説的不眠症の存在自体が議論されてきましたが、定義の不統一が混乱を招いていました。
そのため、本研究では、既存の定義を再評価し、エビデンスに基づいた診断基準を構築することを目指しました。
この論文を読んでから、睡眠法の効果が「主観的か、客観的か」を気にするようになりました。例えば、運動は主観的な睡眠効果はあるが、客観的な睡眠効果は微妙などですね。
ちなみに運動は内容が幅広いので、この逆説性と一緒で、どんな運動が効果があるかをもっとパターン分けして理解したほうが良さそうです。
結果はどうだったか?
1. 逆説的不眠症の有病率
逆説的不眠症の有病率は、使用する定義によって**8%から66%**と大きく変動しました。
- 8%:厳格な診断基準を使用し、睡眠データと主観評価が極端に食い違う場合のみを抽出したケースです。
- 66%:緩やかな診断基準を使用し、睡眠データに多少の異常があっても主観的な訴えを重視したケースです。
このように、有病率のばらつきが示す通り、診断基準の設定が結果に大きく影響しています。
2. 定義間の一致率
診断基準ごとの一致率は、-0.19から0.9と非常にばらつきがありました。
- -0.19:全く一致しない基準同士を比較した場合です。
- 0.9:ほぼ同じ基準を用いた場合で、診断結果がほぼ一致するケースです。
これにより、基準ごとの一貫性が欠如していることが問題視されています。
3. 診断基準の課題
研究を通じて浮き彫りになったのは、診断基準が統一されていないことによる混乱です。
特に以下の2点が課題として挙げられました。
- (1) 睡眠しなければならない最小時間数:短すぎると一般的不眠症として扱われ、基準設定が困難です。
- (2) 総睡眠時間と入眠潜時の取り扱い:睡眠時間が短く入眠までの時間が長い場合、主観的に「眠れていない」と感じやすいが、これをどう診断基準に組み込むかが未解決です。
8~66%にズレる診断というのは、なかなかにびっくりです。
今後は睡眠トラッカーの一般的な浸透により、研究が進みやすくなると思います。その場合はどの睡眠トラッカーを使えばOKか、と考えることが必要ですよね。
睡眠の質はともかく、睡眠時間はかなり精度が高いので、睡眠時間ベースでもどんどん分かってくることを望みます。
まとめ
逆説的不眠症の診断基準は、現在も不統一であり、主観的評価と客観的データをどのように調整するかが課題です。
今後、標準化された定量的指標を確立するためのさらなる研究が求められています。
不眠症で困っている場合は、主観的・客観的はかなり重要と思っています。
主観的であればマインドフルネス系は相性良さそうですし、客観的であればとにかく「体内時計・睡眠圧を整える」など方向性が見えやすいですよね。
出典
本記事の要約には、ChatGPTを使用して研究内容を著作権に配慮して、整理しました。
参考文献:
カステルノヴォ A, フェリ R, パンジャビ NM, 他.
参考:逆説的不眠症のパラドックス:統一的な証拠に基づく定義に向けた理論的検討