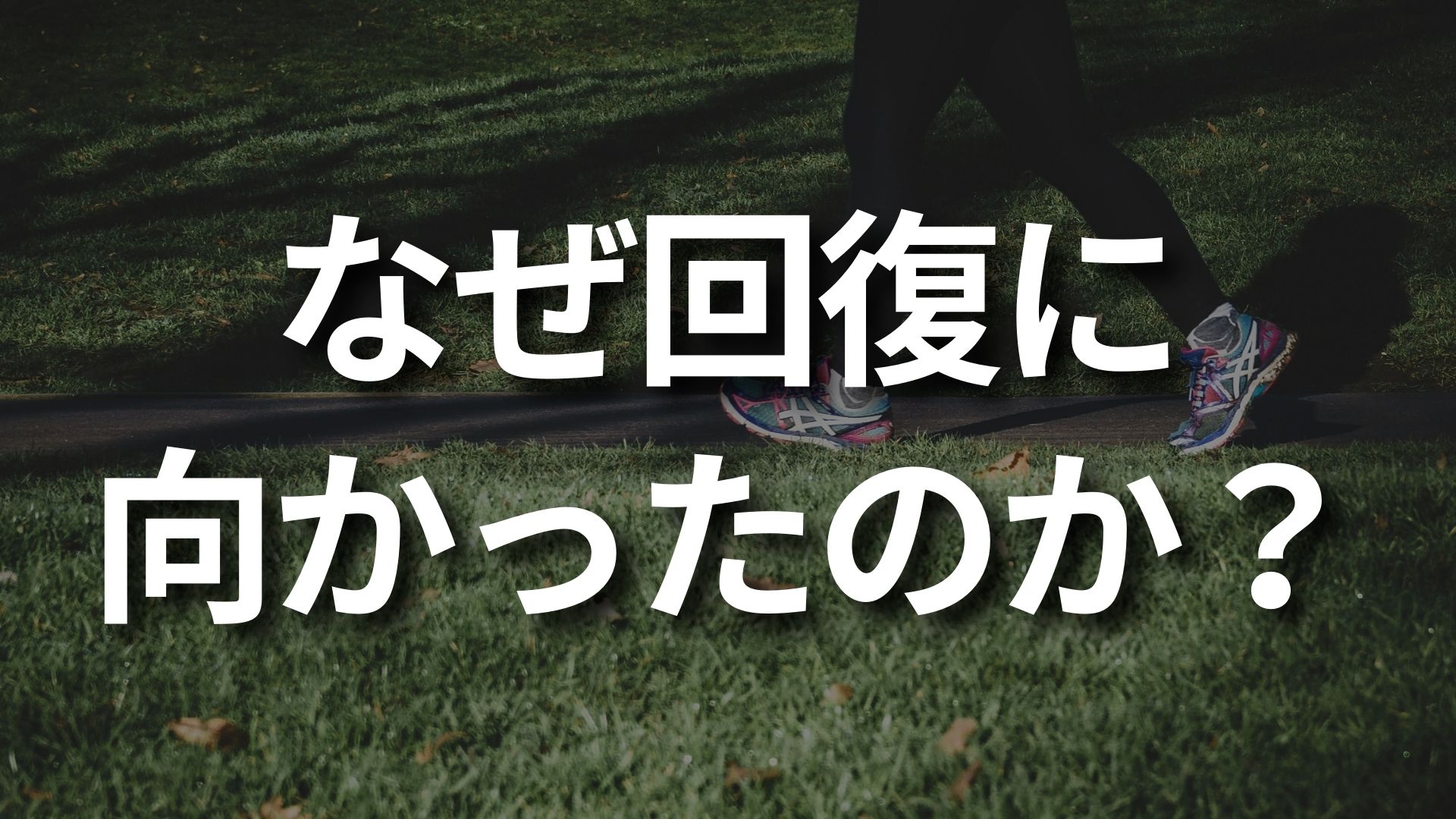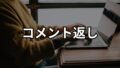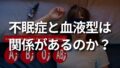メンタルコーチのしもんです。
僕は29歳から5年以上うつを患っていました。実際には双極性障害2型で、長いうつ症状に悩まされていたんです。
無気力と完璧主義から、うつを改善するための行動がそもそもとれませんでした。でも、今回お伝えする方法がきっかけとなり、少しずつ回復に向かっていたんです。
今回はうつが回復するのにとても役立ったものを5つお伝えします。
①前に進むものかどうかで判断
1つ目のきっかけは、「うつを治すではなくて、今よりもより良くなればいい」という考え方に変わったことです。
そもそも「うつを治すこと」が、僕の中ではとても曖昧なものでした。どうすればうつが治るのか方法とゴールが、いまいち分からなかったからです。
「何を目指しているのか?何をすればいいのか?」
それが分からなくて、ただでさえ無気力なのに行動ができなくなっていました。でも、「今よりもより良くなっていく」ぐらいのレベルであれば、「それならある程度何とかできそうだな」と思えたんです。具体的な方法とゴールが見えたからです、
・横になっている時間を減らし、座る時間を5分でも伸ばす。
・カーテンを開けて太陽の光をあびる日数を増やす。
・食器洗いをする日数を増やす など
今よりも良くなればいいという考え方に変わることで、少しずつ前に進んでいく感覚が得られました。このときは、うつが治らなくても「できることを増やせば、今よりもマシになるから、ひとまずはそれ良いか」と考えられるようになったんですね。
うつを治すと考えていた頃は、うつではない自分から今の自分を考えてしまい、減点方式になっていました。でも、「今の自分を少しずつ前に進めると考える」と、加点方式で少し自分を取り戻せた気がしたんですね。
このときから「前に進むもの。数が増えていくもの」をもとに目標や行動を考えるようになりました。
前に進む感覚は「気力を取り戻す」|プログレスの原則
プログレスの原則とは「小さくても前に進んでいる感覚があることが、満足感やモチベーションを高める」という心理です。ハーバードビジネススクールのテレサ・アマビール教授らが提唱しました。
・ドラゴンクエストで「闘うと経験値がたまる。そしてレベルアップする」と、バトルそのものが楽しくなる。
・お店のポイントカードのポイントがたまっていくと「お金以上のうれしさ」を感じる。
・日記を書いているときに「今まで書いてきたノートのページ数」を数えたり、厚みを確認したりすると達成感がある。
こんな感じで人は「前に進む感覚」があると、思わずモチベーションがあがります。
プログレスの原則は「仕事の満足度とモチベーションを高める方法」から生まれていますが、プライベートでも使えます。仕事にすら効果がある方法だからです。
世界的にも「仕事はつまらない」と思う人は多いです。
実際に世界的な調査会社ギャラップ社が140以上の国と地域で調査した結果、「仕事はつまらないと感じている人」は77%と報告しています。
前に進んでいる「達成感」を得ることで、「この行動には価値がある」と確認できるので、仕事ですら満足度とモチベーションがあがるんです。
2.今の自分にとって「できやすいかどうか」
2つ目のきっかけは、今の自分にとって「できやすいもの」に目を向けたことです。
とりあえず「何かを変えなくちゃ」と思っていて、でも動ける時間が少なかったので簡単なものから始めたんですね。
・朝散歩を30分。いやこれはすぐにはできない。まずは朝着替える習慣から付けよう
・本を全部読むのは無理。見出しを見て、興味がある部分だけ読もう。
・呼吸法や瞑想系なら、ベッドに横になっててもできるからしよう。
「それは、簡単にできるかどうか?そして変えられるものかどうか?」を考えると、焦りが減って、心が穏やかでいられる時間が増えました。少しずつできることが増えるので、前に進んでいる感覚があったからです。
できることに集中|コントロールフォーカス
コントロールフォーカスとは、「自分がコントロールできること」に集中することです。
自分ができないものにとらわれると、前に進まず苦痛が生まれやすいです。でも、できるものに集中すると、小さくても前に進んでいくので、自分を取り戻せる感覚が生まれるんですよね。自分の行動をコントロールしている感覚があるからです。
後悔で苦しみを生まれるのも、変えられないものであり、コントロールができないからです。でも、後悔を反省で変えれば、「次はどうすればいいか?」と未来に目を向きます。未来は変えられるので、コントロール感覚が生まれてきます。
買い物に行きたいのに台風で外に出られない時。
嵐をなんとかしようと、外に出て嵐を止めようすれば、単にずぶ濡れになって嫌な気持ちになります。でもコントロールできることに目を向ければ、行動の選択肢が見えてきます。
・家の中で好きな映画を見る。
・台風がいつ過ぎ去るかニュースをチェックする
・次に買い物するときのリストを作っておく。など
発想を変えれば、外で出て、台風の中で雨に打たれるのを「レア体験」として楽しむ方法さえあります。
台風で考えると、「台風を止めようとするなんてバカバカしいよな」と多くの人は思うものです。でも、「コントロールできないものをがんばろうとすること」は意外にたくさんあります。僕の場合であれば「過去にできたことが今できないことに落ち込む」などがありました。
3.今の自分にとって「役立つかどうか」
3つ目のきっかけは「今の自分にとって役立つかどうか?」で考えるようになったことです。
知識にしても道具にしてもアイデアにしても、「役に立つもの」と「役に立たないもの」があります。なので、「今の自分に役立つものだけに集中」しました。
例えば、本や記事を読むときに、今の自分に役立つところだけ読む。他は読み飛ばしていました。
【仕事でのタスク管理法は~】。
今、仕事していないから役立たないけど、この優先順位の付け方は今の自分にでも役立ちそうだな。ここだけ読もう。
【稼ぐのフェーズを超えたら、お金がお金を生み出す仕組み。投資が~】。今、そもそも稼ぐことができていないから投資は役立たないけど、この貯金や出費を抑える考え方、今の自分に役立ちそうだ。ここは読もう。
今の自分に役立つ情報だけを読むと、手軽で早く読めます。しかも今の自分に役立つので、現実を前に進めるスピードが速くなります。
【役に立つものこそ真理】道具主義とは?その哲学的背景と現代社会における役割を徹底解説
4.自分を思いやる心を育てた
4つ目のきっかけが、うつ回復に最も役立った「自分を思いやる気持ちを育てたこと」です。
自分を思いやることができた結果、現在と未来の両方を意識した行動がとりやすくなったからです。
自分のことがどうでもいいと思っていると、「自分を傷つける」や「目先の喜び」に捉われることが増えます。
自分のことを「どうでもいい」と感じていた頃は、
・人に助けを求められないようにスマホを割る。
・ステンレスなど固いものに拳を打ち付けて手を使えなくする。
・自分を困らせるために薬を捨てる。
といった、「自分を傷つける行動」が増えていました。
また、
・カーテン開けて眩しいのが嫌だから、カーテンを開けない。
・深く呼吸するのがだるいからしない。
・栄養があるものではなく、お菓子など食べやすいものを食べる。
といった「目先の楽」にとらわれることも多くなっていました。
でも、「自分を思いやる気持ちが育つ」と、自分を傷つけないばかりか、自分のために少しがんばる気持ちが芽生えてきます。
「面倒だけど、自分のためにカーテンを開けてみよう」
「ゆっくり深呼吸を3回しよう。少しでも心が楽になるように」
「お菓子ではなく、もう少し栄養のある目玉焼きをつくろう」
そんな「自分を守る行動」がしやすくなってきます。
「自分」を思いやる力|セルフコンパッション
自分を思いやる力を育てるのが「セルフコンパッション」です。
セルフというので「自分」がクローズアップされがちですが、実際には「世界とつながっている自分を見つめ思いやること」です。
他の言い方だと、風の谷のナウシカの「個にして全、全にして個」、鋼の錬金術師の「一は全、全は一」です。セルフコンパッションのセルフとはこういった「自分の捉え方」になるからです。ここを意識するだけでも、セルフコンパッションの心をうまく育てやすくなります。
僕がメインに行っていたのは、セルフコンパッション日記です。
内容は認知行動療法に「自分への思いやり」を付け加えたようなものです。僕の場合、はじめはうまく書けなかったので、感謝日記からセルフコンパッション日記に少しずつ移り変わっていきました。感謝とセルフコンパッションにつながりがあるのも、先ほどの「個にして全、全にして個」が根底にあるからです。
5.「すっぱいブドウ」で考えるのをやめた
イソップ童話に「すっぱいブドウ」の話があります。
ある日、キツネが美味しそうなブドウがたわわに実っているのを見つけました。キツネは「なんてうまそうなんだ!」と思い、何とかしてそれを取ろうとジャンプを繰り返します。でも、どんなに頑張ってもブドウには手が届きません。やがて疲れたキツネは、ブドウをあきらめてこう言い残します。「ふん、どうせあのブドウはすっぱかったに違いないさ。」
そして、何も取らずにその場を立ち去ったのでした。
僕の場合は、行動する前に「こんな行動しても無駄だ」と、行動をしなかったことが多かったんですね。「どうせすっぱいブドウだ」と考える心理と同じです。そういった意味ではイソップ童話のキツネさんはブドウを取ろうとジャンプしている分、当時の僕よりは間違いなくかっこいいですね。
5つ目のきっかけは、「行動する前に、行動をネガティブ評価するのをやめたこと」です。「すっぱいブドウと考えるのやめて、食べなきゃ分からない」と考えるようになったんですね。
うつ病に科学的な効果がある行動活性化療法
行動をやる前に判断せずに、行動してから判断する「行動活性化療法」の考え方は重要です。
人は行動する前に「良い悪い」の評価をしがちですが、実際に行ってみるとその評価は間違っていることが多いです。計画や準備も大切ですが、「まず小さくやってみる」と、思いのほか早く前に進めることがあります。
「成人のうつ病に対する15の証拠に基づく療法の効果」のメタ分析では、行動活性化療法(1.05)は認知行動療法(0.73)よりも効果が高いと報告しています。うつ病になると「行動しないことで心身が弱ること」があるからです。
行動する前に「これをやっても意味がない」「こんなことをしたら疲れてしまう」と考えるのではなく、まず「小さく行動」してみる。
行動が増えることで疲労回復で大切な3つの要素「肉体的な回復」「精神的な回復」「社会的な回復」がうまく行き始めます。また、うつ病や認知症の人の大きな原因と言われる「脳の成長栄養BDNF」を増やすことができます。
さいごに:知識を道具に。そしておもちゃに。
最後まで話し終わって、ふと思うことがありました。
「最近は自分の感情を楽しませる工夫をサボっていたな…」と。
特に無駄を削る意識が強くて、感情の満足感まで削っている部分がありましたね。たまに振り返りとしないと、「思わず自分が望む道からそれてしまうことがあるんだな」と実感しました。
知識を道具のように使うのではなく、ときにはおもちゃのように楽しく使っていきたいですね。
今回の動画は、1年前に顔出し動画で配信したテーマですが、あらためて配信できて良かったです。リクエストをくれていたクマさん、イオさん、ヨシエさん、ありがとうございました。