こんにちは、上級睡眠健康指導士のしもんです。
今回は「中途覚醒の治し方5選」をテーマにお伝えします。
「夜中に目が覚めるのは、浅い眠りで睡眠の質が良くない」と思うことがありますよね。
僕も以前は夜中に目を覚ますのは、睡眠においてダメなことだと思っていました。
でも、違っていたんです。
最近の睡眠事情を報告すると、 以前と同じく入眠には問題はありません、また中途覚醒については 夜中目は毎日覚めていますが、 30分以内にはほとんど寝れている感じです!! また朝起きた時の不快感が軽減されました!たぶん自分の中で中途覚醒に対する認知が変わってきたからだと思います! しもんさんの動画のおかげです!
YouTube動画コメントより
また、この動画でしもんさんがおすすめしていた30のカウントダウンを実践するようにしています! 想像以上にうとうとするので、 自分にはこの方法は合ってるなあと感じています! 紹介して下さりありがとうございます!
この記事の内容は動画で視聴できます。
「夜中に目が覚めること=悪いこと」なのか?
夜中に目を覚ました後で
すんなり眠れるようであれば特に問題がありません。
夜中に目が覚めること自体は、ほとんどの人にとっては普通のことだからです。
人は1晩に約2~3回(もう少し多い人もいる)ほど目が覚めています。
目が覚めた時の記憶が残っていないので、朝までぐっすり眠れたと思っていることが多いのです。
なぜ ほとんどの人が2~3回ほど目が覚めてしまうのか?
人は一晩のうち、浅い睡眠と深い睡眠を繰り返しています。
簡単にすると浅いノンレム睡眠→深いノンレム睡眠→レム睡眠です。
浅い睡眠になった時に、何かのきっかけによって目が覚めやすくなりやすくなります。
何かのきっかけというのは、さまざまです。
体の中からくる刺激であれば、
尿意とか口の渇きなどによって目が覚めるなどです。
体の外からくる刺激であれば、
熱すぎる、寒すぎるなどの気温や、音や光などです。
目が覚めやすい状態は、想像以上にたくさんあります。
ほとんどの人が夜中に目を覚まして、すんなり眠っているので記憶に残っていないだけなんです。
睡眠周期は約80~100分で繰り返しています。
周期ごとに浅い睡眠がおとずれるので、目覚めてしまうタイミングは複数あります。
夜中に目が覚めたときに問題なのは、再入眠できるかどうか
起きた時に気にしなければすぐ眠れるものです。
睡眠慣性が働くからです。
睡眠慣性っていうのは簡単に言うと「寝ぼけ」ですね。
朝に目が覚めた時に眠いなーと思って、2度寝をしてしまった経験はありませんか?
起きた時にまだ睡眠の感覚が残っていて(睡眠慣性)、もう一度そのまま寝てしまうからです。
頑張って起きようとしたり、起きないとやばいなど感情がひも付かなければ、自然とまた眠くなって寝てしまいます。

中途覚醒の場合。
夜中、目が覚めた時に時計を見て、
「中途半端な時間だな。いやだなぁ」
「すぐ寝れるかな」
「明日も仕事だし寝ないと」
ネガティブな感情がうまれ、プレッシャーや頑張って睡眠しようとしてしまうと、再び寝つくのが難しくなってしまいます。
基本的には夜中に目が覚めても、気にしなければ そのまま自然と寝入ってしまうものです。
もちろん すべての人とは言えませんが。
多くの人は夜中目が覚めても気にせずに
目をつむってリラックスしていれば
そのまま眠れてしまうことの方が多いのです。
でも、夜中起きた時に気にしないと言われても、難しいですよね。
難しいのは当然と言えば当然なんです。
気にしなくてもいいと言って、気にしないことができるのはかなり難易度が高いからです。
普段、瞑想などしていて、マインドフルネスの力が高い人は、簡単にできるかもしれません。
でも、ほとんどの人の場合、気にしないと思えば思うほど気にしてしまうものです。
例えば
次の文章をしっかり読んでください。
「シロクマのことだけは絶対に考えないでください。
絶対に考えてはいけません。
シロクマをイメージしちゃダメですよ」
どうでしょうか?
おそらくあなたはシロクマをイメージしたり、シロクマのことを考えやすくなっていませんか。
しかも、シクロマを考えないようにすればするほど、シクロマがイメージしやすくなるはずです。
「シロクマのことをイメージしちゃいけない」
「シロクマのことを考えてはいけない」
思えば思うほど
シロクマのことが思い出されてしまうのがシロクマ実験なのです。
>【シロクマ実験】いろいろと考えすぎて眠れないときの対処法とは?
同じように夜中に目が覚めた時
・時計を見ちゃいけないと思うと、時計が見たくなる
・中途覚醒を気にしちゃいけないと思えば思うほど、気にしてしまう
・眠らなきゃいけないと思うと、眠れない自分を意識してしまう
もしも、夜中起きた時に「気にしないことができる」のであればOKです。
でも、「分かっているけど、気にしてしまうんだよ」という場合は、今回の5つの方法を試していただければと思います。
①スロー・カウントダウン
②ライトハンド
③無呼吸症候群か確認
④運動習慣をつける
⑤睡眠環境を整える
①スロー・カウントダウン
1つ目はスローカウントダウンです。
数字をカウントダウンするだけで
頭の中の不安であるとか焦り
眠れないという意識がなくなっていく
マインドフルネス的な方法です。
実際にどのようにやっていくかと言うと、
30からゆっくりとカウントダウンしていくだけです。
実際やっていただけたら、すごく効果が実感しやすいと思います。
30-29-28…とゆっくりカウントダウンしていくと、
カウントダウンすることに意識が奪われて
他のことが考えられなくなっていきます。
そして、そのままストンと眠ってしまうという方法なのです。
②ライトハンド
2つ目はライトハンドです。
ライトハンドとは、
1つ目のゆっくりカウントダウン同じで
集中力を使ったマインドフルネスの方法です。
方法は。
夜中に目が覚めたとき
ベッドの上に置いた右手を
目をつむったまま感じ取っていく。というものです。
手のひらがどのような握り具合か?
少し曲がっているのか?
完全に開いているのか?
ギュッとしているのか?
次に指に意識を向けていきます。
例えば
人差し指の第一関節はどのように曲がっているか?
人差し指の指先はどのような温度を感じるか?
どのような空気が触れているか?
手や指に集中して、感じ取っていくと
他の事が考えられなくなってきます。
夜中に目が覚めた時に
ライトハンドをしてもらって
まず指先に意識を向けて
そっちに意識が囚われている間に眠気が来て
ストンといつのまにか眠ることができるテクニックです。
③無呼吸症候群か確認
無呼吸症候群はおそらく聞いたことがあると思います。
無呼吸症候群も中途覚醒に繋がりやすいものです。
いびきをかいたり、息苦しいので目が覚めやすくなるんです。
ただ、僕もそうだったんですけど、
無呼吸症候群って勘違いが生まれやすい症状なのです。
無呼吸症候群は
肥満な人や太っている人しかならないと勘違いされています。
無呼吸症候群は太ってなくても起きる症状です。
僕も過去を振り返ると
うつ病と不眠症が両方あったときは
無呼吸症候群だったのかな?と症状がありました。
夜中にぐーぐー寝ていた時に、
途中で息苦しくなって起きてしまう。
息がうまくできない、ということが度々あったんですね。
そんなに太ってはいなかったのに…なんでだろう?と思っていました。
無呼吸症候群=肥満の人がなるものと思っていたので、無呼吸症候群だとは自分の中では一切思っていなかったです。
なんか息が止まっていたような気がする。
いびきをかいているのは最近疲れているからかなーとか思っていました。
実は骨格や肉付きなどの遺伝要素もあるのが無呼吸症候群です。
僕って骨格がやや小さいんですよね。
多分、骨格の小ささから無呼吸症状が起きていたと思うんです。
骨格が小さいので少しの肉付きでも、呼吸が窮屈になって、無呼吸症候群が起きる仕組みですね。
無呼吸症候群は無自覚であることが多いと言われています。
気になる方や家族と一緒に住んでいる方は、
自分が寝ている時に呼吸が止まっていないかどうか、
チェックしてもらうように頼んでみてくださいね。
無呼吸症候群が原因の不眠症は、無呼吸症候群を治すことによって、改善します。
ぱっと眠れるようになってくる可能性もありますので、一度調べてみることをおすすめします。
自分は「やせているから無呼吸症候群にはならない」と思わずに、一度チェックをしてみるのがおすすめ。
無呼吸症候群は、睡眠薬に関わってきます。
睡眠薬の中には脳に作用して、眠りに向かわせるものがあります。
でも、睡眠薬として処方されるものの中には、体をリラックスさせることによって、眠らせるものもあるんです(寝る前に飲んでねと言われていて、薬を調べると抗不安薬だったりする場合ですね)
無呼吸症候群がある方が、
筋弛緩(リラックス)の効果のある
睡眠薬・抗不安薬などを飲んでしまうと、
より無呼吸症候群が悪化してしまう可能性があります。
なぜかと言うと、
筋弛緩効果があるので、体の筋肉がゆるむからです。
筋肉がゆるむっていうことは、より呼吸が狭くなってしまう可能性があるんです。
④運動習慣をつける
運動すると熟睡できるといわれますよね。
でも、運動してもなかなか寝付けないことはありませんか?
運動が睡眠にうまく繋がるかどうかは個人個人によって変わります。
運動して疲労感があるから、そのままゆっくり眠れる人はいます。
一方で、疲労感がストレスになってしまって、逆に眠れないという方もいらっしゃいます。
特に運動量が足りないと思い、運動を無理に頑張りすぎてしまうと、
関節にダメージが出てきたり、
筋肉痛などになったりなどして、
痛みの刺激が夜中に起きるきっかけとなり、
中途覚醒が発生しやすくなることもあります。
ではなぜ、ウォーキングなどの運動が睡眠には大事だよと言われるのか?
運動による心地よい疲労感から眠れるというのも、もちろんあります。
でも、運動の効果は、運動習慣がつくことで体が健康になっていくからです。
筋肉がついたり、脂肪が減ったりなどして体が健康的になります。
体が健康的になった結果
・脂肪による体内部の刺激が減る
・姿勢のゆがみによる寝苦しさが減る
・脂肪が減ることと、呼吸器系が鍛えられ呼吸がしやすくなる
・筋肉がつくことで、頻尿がゆるやかになる
などの理由があり、夜中起きにくくなります。
もちろん、運動して眠れるんであればそのままでOKです。
運動してもなかなか眠れない場合でも、運動を習慣化していくことは大事です。
運動をするときのコツは「心地よい疲れ」ぐらいの運動にすることです。
心地よい疲れの運動の強さは人それぞれなので、お気を付けくださいね。
⑤睡眠環境を整える
まとめ
①スロー・カウントダウン
②ライトハンド
③自分が無呼吸症候群か調べる
④適切な運動習慣をつける
⑤睡眠環境、温熱・光・音の3つを整える
最後までお読みいただき、ありがとうございました。



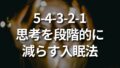
コメント