ある病院の面白い話があります。
田中さん「なかなか眠れない。不眠症が長く続いていて困っているんだ」
スタッフ「分かりました。ドクターを呼ぶので、少し待っててくださいね」
田中さん「はい」
スタッフ「疲れていると思うので、ベッドの上で横になって起きたまま待っていてくださいね」
田中さん「わかりました」
田中さんは病院のベッドの上で横になって、起きたまま待とうと休んでいると。
しばらくして、すやすやと気持ちよく眠ってしまいました。
という風に、眠ろうと思うと眠れないけど、起きていようと思うと眠れてしまう、ということがあります。不思議なものですね。
あなたも次のような体験をしたことはありませんか?
- いっそのこと徹夜してやる!と思うと、だんだん眠くなって寝てしまう
- 朝まで眠れず、あと2時間で起きる時間だからいっそ起きようと思うと、眠くなる
- ベッドだと眠れないけど、ほかのところだとうたた寝してしまう
- 電車に乗っているとうたた寝する
- 読書やYouTubeなど別のことをしていると眠たくなって、うとうとする
- 人の話を聴いていると眠くなって、うとうとする
- 眠るのをあきらめて、スマホをさわっていると眠れてしまう
もしも、普段なかなか眠れないのに、当てはまる体験があるのであれば、あなたの眠れない原因は「睡眠へのプレッシャー」にあります。
ちなみに箇条書きの体験はすべて、僕の実体験です。
そして、逆説的意図睡眠法で眠れる可能性がある体験でもあります。
睡眠へのプレッシャーがあると眠れない
眠れない日々を過ごす人にとって大きな障害が「睡眠へのプレッシャー」です。
特に眠れない体験をたくさんしている場合、睡眠への意識が強くなりすぎることがあります。
その結果、「今日は眠れるかな?」「眠りたい!」という不安や緊張が、眠りではなく目覚めにつながります。
特に頑張り屋、完璧主義、まじめなかたがハマりやすい睡眠の罠です。
この睡眠プレッシャーで眠れなくなるのが精神生理性不眠症です。
「だったら、どうすればいいんだ!」と思うかもしれませんが、原因が分かっていれば解決もしやすくなります。安心してください。
今回であれば、睡眠へのプレッシャーを失くすことが鍵になります。
睡眠の裏技:逆説的睡眠法とは?

逆説的意図睡眠法とは「眠るではなく起きる」と逆のことを考えることで、睡眠のプレッシャーをなくしていく思考です。
具体的にはどのように考えるか、というと次のような方法をとります。
逆説的意図睡眠法の手順
①よく眠る人は何をするだろうかと自問。
「眠る人は睡眠について考えず、眠るために特別なことはしない。」
②睡眠に「期待しない」
③いつも通りの時間に就寝し、目を開けたままにする。
④起きているつもりで、無理をしない。
⑤「数分だけ起きていよう」と自分に言い聞かせる。
⑥刺激的な活動をしない。
睡眠のプレッシャーが減ればOKなので、この方法にこだわりすぎず、次のような方法をとってもいいです。
思考の場合(逆説的思考)
・実際にベッドから出て、起きて何をするかを考える
・もう寝ない!がんばって起き続けるぞ!と考える
・朝まで起きておこうと考える
・もう寝ないぞと考える
行動の場合(逆説的行動)
・ベッドから出て、別の部屋や椅子で過ごす
・ベッドから出て、ストレッチをする
・ベッドから出て、薄明かりをつけて読書を静かにする
あまりおすすめではないですが、睡眠のプレッシャーのみが不眠につながっている場合、「スマホを見る」「YouTubeを見る」「テレビを見る」など、完全に起きるにつながる行動をしても眠れる場合があります。
「眠ることをあきらめること」ができると、ついつい眠ってしまいます。
睡眠の裏技:逆説的睡眠法の3つの効果
「不眠症に対する効果的な介入であり、特に睡眠の開始と維持の困難を軽減し、睡眠後の休息感を高めるのに効果的」
不眠症に対する逆説的意図:系統的レビューとメタ分析2021年
以上の研究によると、次のことが分かります。この研究をまとめたもの
- 寝つきがよくなる
- 中途覚醒が減る・目覚めても再入眠しやすい。
- 熟睡感がある
逆説的意図でなかなか眠れない場合
逆説的意図の考えで眠れない場合、睡眠へのプレッシャーだけが原因ではなかった可能性があります。
ただ原因が違っただけでなく、そもそも逆説的意図がうまくできていない可能性もあります。
というのも、「逆に起きると考えるんだ!」と思うときに「起きると考えたほうが、眠れるから!」という意識が強いと、睡眠のプレッシャーが残ったままになるからです。
「起き続ける!」と思ったら、「じゃあ、これから何しようかな。朝まで6時間あるからいろんなことができるぞ」みたいに、眠ることをあきらめることができるのがポイントだからです。
ちなみに、僕は逆説的意図睡眠法をうまく使えるときのほうが少ないです。
だったら、「どうして逆説的意図睡眠法をおすすめしているの?」と思われるかもしれません。
理由はとても簡単で逆説的意図睡眠法は「ものすごい手軽だから」です。
特に準備も必要なく、知識も必要なく、ただ眠るときに「このまま起きていよう」と思えばいいからです。
「眠れたらラッキー」ぐらいに今夜から試していただける方法です。
そして、「眠れたらラッキー」ぐらいに軽く考えたほうが睡眠へのプレッシャーがなくなり、逆説的意図睡眠法は成功しやすくなります。
逆説的意図睡眠法に代わる「同じ効果の睡眠法」
逆説的意図睡眠法がうまくいかない。でも、睡眠のプレッシャーが原因なのは間違いない。
どうすればいいんだ!
というときは、次の方法をお試しください。
- スマホの「認知シャッフル」アプリを使う
- 扇風機の音など自然音に近い雑音を流す
- 部屋を真っ暗にせず、薄明りにする
- ヒーリングミュージックなどの音楽を聴きながら寝る
以上の方法は、「眠らなくちゃいけない!」などの睡眠への意識の強さを、小さな刺激によってやわらげてくれます。
相性はありますが、認知シャッフルのアプリは手軽なので試しやすいです。
睡眠の裏技:逆説的意図睡眠法のまとめ
- 眠ろうと考えすぎると、睡眠へのプレッシャーが生まれ眠れなくなることがある
- 眠ろうと力が入るときは、起きるようと逆に考えると、眠れることがある
- 眠る意識を手放すことが、眠れることにつながる
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
それではまた、次の記事でお会いできることを楽しみにしています。

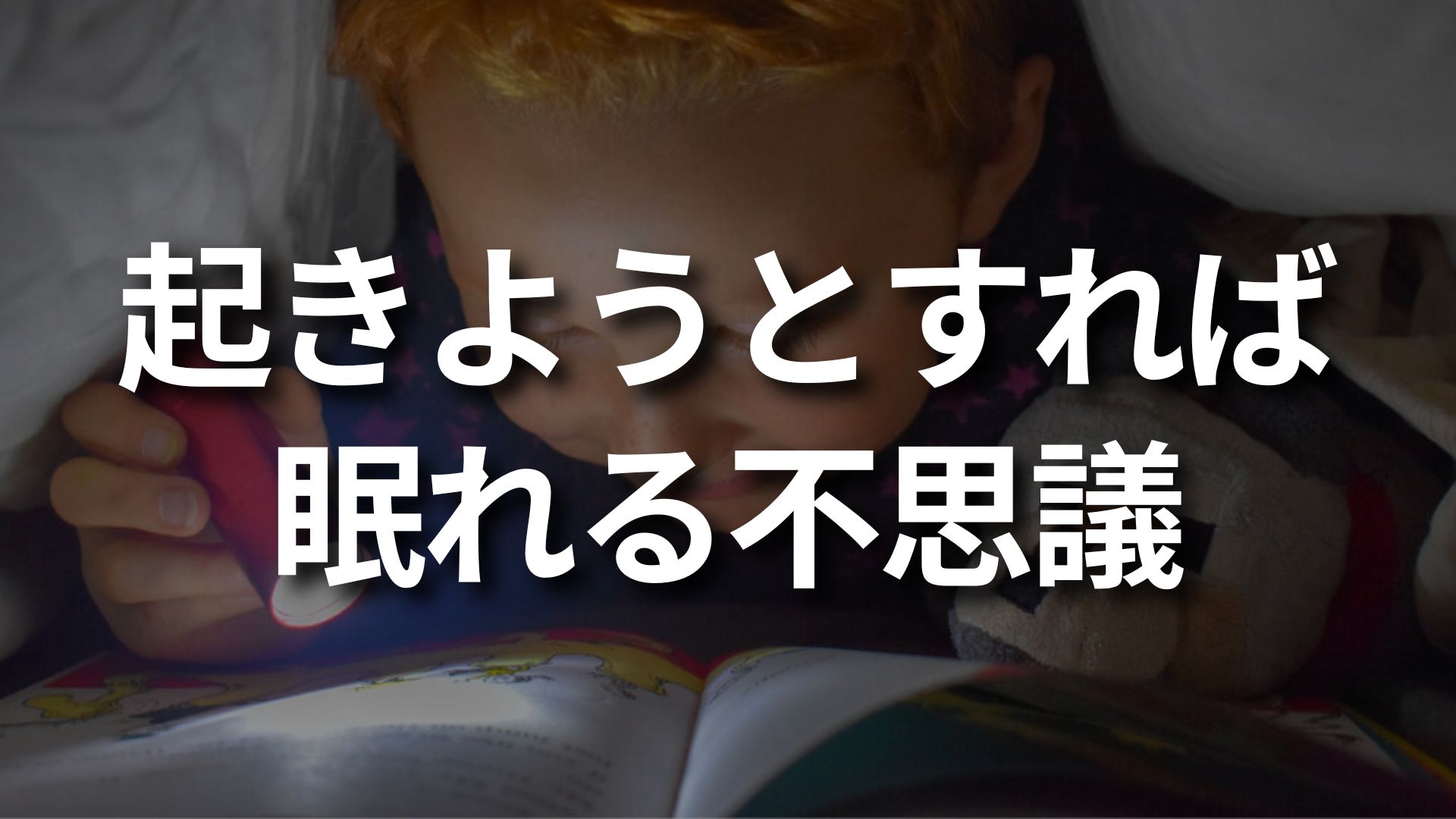


コメント